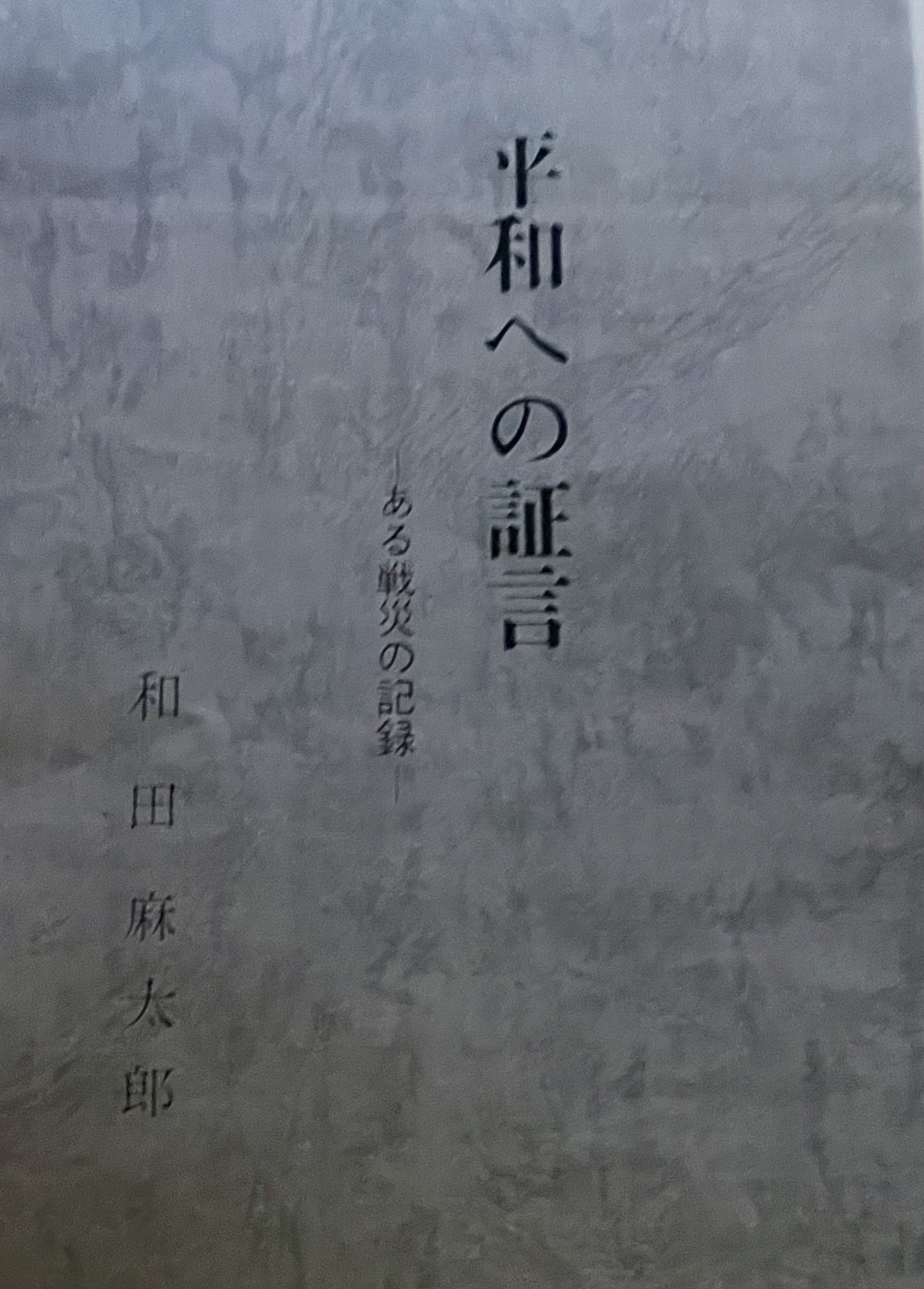露軍将校遺体漂着記念碑を訪ねよう露軍将校遺体漂着記念碑は、明治38年(1905年)5月27日に終わった日本海海戦のバルチック艦隊撃滅の時、約3週間後に、田後港の沖合で発見されたロシア将兵遺体を漁師が港へ連れて帰り、敵国であれど同じ人間だ、仏になったなら丁重に供養するがよかろう、と判断し地元の村民が葬儀を営み、埋葬したことを記念しています。(のちに詳細解説)露軍将校遺体漂着記念碑は鴨ヶ磯展望台から階段を降りて、城原海岸へ向かう方向(右)に歩き、椿谷に入る手前の遊歩道にあります。現地の案内版との差異もあり、鳥取県の調査による情報の補足にもなりますが、明治38年6月17日に田後港から2〜3キロ沖を25歳くらいに見える1遺体が(漂流)しているのを漁師さんが連れ帰り露軍だという事は着衣でわかりますが氏名などは不明でした。また翌日、出航した船が1遺体を見つけ、港に帰港する船に預けた、との事です。着衣の遺留物から氏名は判明しており年齢は35歳くらいに見えたそうです。更に6月27日には城原海岸の洞窟に30歳くらいの着衣の無い1遺体が漂着していて、この遺体も椿谷に葬られたと思われます。 そのことから発見日はすべて別日で計3遺体が埋葬されました。この際、田後は網代との村境、敵国の遺体をなぜ…と言う事で賛否に分かれることは人の感情としては当然のことで…村の意見は割れたことは事実です。しかし、冒頭に書いたように『敵国であれど同じ人間だ、仏になったなら丁重に供養するがよかろう』という結果を出し、村境に埋葬したようです。その後、日本政府(軍部)はロシア兵の遺体(対馬 山口 島根などの漂着、捕虜の死亡)を全国3ヶ所の外国人墓地にまとめるとし、椿谷の遺体は掘り上げて長崎のお寺に移しました。また6月26日に羽尾の海岸にも30歳くらいとみられる1遺体の漂流が発見されました。隣海院で法要をして羽尾村の共同墓地に埋葬しましたが、山陰線路敷設の為山側に移動しました。墓石は今も残っており、毎年のお盆とお彼岸には花が手向けられています。平成 6 年 5 月に埋葬地付近に「露国軍人碑」を建立しました。この遺体も長崎に送られたと思われますが、県に記録はありません。 なお、長崎のお寺は昭和20年の原爆で破壊し多数の墓碑が消滅し、鳥取から改葬されたロシア兵を確認することはできない状況になってしまいましたが平成8年に再興され、外国人墓地『稲佐悟真寺国際墓地』に慰霊碑があります。悟真寺(ごしんじ)は長崎県長崎市にある浄土宗の寺院で正式名称は終南山光明院悟真寺です。本尊は明国由来と伝えられる阿弥陀三尊像で長崎市に現存する最古の寺院です。所在地: 〒852-8008 長崎県長崎市曙町6−14露軍将校遺体漂着記念碑建立と交流までの歴史その後、昭和37年に村民の「人類愛」の精神を顕彰するため、初代国連大使で岩美町出身の澤田廉三さんによって鴨ヶ磯海岸の椿谷に露軍将校遺体漂着記念碑と碑文石が建立されました。澤田夫妻の精神である母子愛・祖国愛・人類愛の『三愛』のひとつです。しかし、時が経過するにつれ、この人間愛という出来事や露軍将校遺体漂着記念碑があることを知らない若い人たちが増えてきました。澤田廉三さんの遺徳をしのび、このまま葬ることは同郷の一人として、また日本人として許されない!っと感じた岩美町浦富出身の和田麻太郎さんが、岩美町の郷土文化研究会会長の吉田正博さんと相談し、全国の人に広く知ってもらい、ソ連(ロシア)と文化交流をし友好を深めたいと決意し活動をし始めたのが昭和62年の事です。外務省や日本対外文化協会、ソ連大使館(当時)、領事館などにこの話を持ち掛け走り回りました。その成果もあり翌年昭和63年5月15日に露軍将校遺体漂着記念碑の前で慰霊祭が開催しました。慰霊祭にはソ連大使館のY・D・クズネツォフ公使夫妻とソ連国営ノーボスチ通信社東京支局長のアレクセイ・K・バンテレーエフ夫妻が参列し、83年ぶりに戦死した2人の将兵をしのびました。この日は田後小学校、岩美中学校、岩美高校のブラスバンド隊の演奏で温かく歓迎し、遊覧船にて浦富海岸の観光、浦富小学校にて子どもたちが描いた絵の贈呈、陸上地区の勝海院での法要、そして、この碑を建立した澤田廉三さんの遺品展を鑑賞しました。さらに同日、『祖父が露兵を埋葬した』という浜坂の吉田さんが静かに待ち望んでいました。思いがけない告白に驚いたクズネツォフ公使は祖父の写真を見ながら何度も握手を交わしたそうです。後日、『今日のソ連邦1988年6月15日号』にアレクセイ・K・バンテレーエフさんにより慰霊祭に参列されたことにについての記事が発行されました。開催にかかわった人たちへの感謝、岩美町、田後の人々が誇りに思う『人類愛』についての受け止め、この気持ちを現代も日ソ(当時)という隣り合う両国民の友好善隣関係の確立と強化に受け継がねばならないと強調し、クズネツォフ公使は日本海で戦死したロシア人水兵の慰霊に寄せられた配慮に心から感謝し、ソ連と日本の岸を洗うこの海は隣国民同士の友好と協力の海となり、慰霊碑と、今回の行事は相互関係のシンボルになると確信すると述べたそうです。その後、5年毎にロシア外交官が訪れ献花を行う「露国将兵慰霊祭」が催されています。(現在※ウクライナとの戦争により中断しています)私たちは露軍将校遺体漂着記念碑までのガイドも行っていますのでよろしければご活用ください。ブログレポート:岩美町のロシア兵漂流記念碑のガイドを行いました。和田麻太郎さんが拓いた友好関係記念碑に関しては澤田廉三さんの名が連なっていますが、この慰霊祭による友好関係を拓いた立役者は岩美町出身で東京で家具製造業を営んでいた和田麻太郎さんです。和田さんは岩美町浦富出身で大正3年の14歳の頃に大阪に出てなんとか仕事を開拓し、工場を構える経営者になりました。一度浦富に戻ったのが昭和16年、しかしその後17年に、東京に上京しました。商店を構えるべく準備をした矢先に戦争の招集を受け、店をたたむことに。しかし、視力検査におち、その日に除隊、また東京に戻って目の前に思いつく仕事をしながら終戦まで様々場所で難を逃れながら戦後の苦しい状況も乗り越えて生き延びてきました。(除隊された際に戦地に向かったグループは全員行方不明で還らぬ人になったそうです)和田さんは岩美町への郷愁は強く、都心部で仕事で成功していく一方で常に岩美町のために何かできないかとばかり考えていたそうです。岩美町に桜やアジサイを贈ったりと出来ることを重ねていました。戦後昭和27.8年ごろ、日米関係が深まるにつれ、ソ連とも交流しなければ…と思いつき、ソ連大使館を日参し、当初は子供同士で絵の交換などができないか?など考えていたそうです。なかなか思うようにいかず、時が流れて昭和62年の事、里帰りした際に、知人でもあった澤田廉三さんが建立した記念碑が人々に忘れ去られ、草に覆われる状態になっていたころ、長い月日をかけてきっかけを掴み、この慰霊祭への熱意が行動に現れました。余談…桐山城跡に公園を創ろうと計画したこともあるそうで、この意思は現在、いわみガイドクラブの油浅会長が引き継いで毎年登山道整備など一人でもコツコツしている!けどメンバーが高齢化で継続が厳しいということも知っている…涙と、話は戻り。慰霊祭にソ連大使館を招待したい!という和田さんは何度もソ連大使館に出向き、大使館から承諾が出たものの現実的に迎えることが難しかったのです。慰霊祭を実行しようとする頃はソ連が崩壊、ロシアへ移行する時期にあたりました。 ソ連の公使が鳥取県にしかも岩美町を訪れる事は当時とてもとても大変な事でした。公使夫妻に万一の事があってはいけないのは当然ながら、その警備は県には経験のない事です。(県は実のところ実現は反対したいと思っていたらしいです)しかし和田さんの熱い想いを受けた岩美町の郷土文化研究会会長の吉田正博さんが、小さな田舎町にソ連大使館を招くなんて叶わない願いだとわかりつつも行動に移したのです。その行動は岩美町長に直談判としてあらわれ、やっとの思いで実現したのが前述の慰霊祭です。その後、岩美町ではウラジオストクに桜並木を作る運動(苗木200本)や医薬品や食料を送るための町民からの募金(155万円)など独自で交流活動を行っていました。このことを知っている町民ももう少ないでしょう。このように日ソ親善を深め続けた岩美町は東京でゴルバチョフ大統領の歓迎レセプションが行われた際に当時の沢徳次郎町長が出席しました。小さな町の町長が国際的な場に参加できるのは本当に稀なことです。和田麻太郎さんは日本対外文化協会から感謝状を贈られるなど日ソ友好関係に尽力し、1989年7月4日に天に召されました。和田麻太郎さんは人類愛だけでなく、岩美町にもたくさんの桜を贈り、学校の図書館には本を進呈し、郷土愛にあふれていました。自身の戦争体験をつづった『平和への祈り』や『故郷の夢を見た』という著書があります。岩美町が空襲に遭った時の体験談含む平和への祈りを読んだ感想はあらためて記載します。チ号演習とグラマン戦闘機の岩美駅襲撃2025年4月、どなたかが碑に献花されていました。
いわみのあしあと・歴史と観光と暮らしの記録
「 岩美町 戦争 」の検索結果
-
-
第二次世界大戦中の岩美のチ号演習と塩づくり鳥取県岩美町では第二次世界大戦では大阪や兵庫など比較的都心部の人たちの疎開を受け入れる側でした。昭和20年に入ると空襲が激しくなり各地で被災した人々が増え、生きていくことに困難を抱える非常事態でした。そのことについて岩美町出身の和田麻太郎さんは手記を残しており、記録によると東京、名古屋、大阪での空襲を目の当たりにして危機一髪で逃れ、地元浦富にかえって田畑を耕していましたが、そのころ岩美では町会単位で塩不足のため東浜海岸など、日本海に面する海岸で塩づくりに勤しみ、チ号演習にも参加していました。チ号演習とは、太平洋戦争末期の鳥取県で実施された陸海軍の秘匿作戦で、敵の九州上陸を想定し、「勤労義勇隊」の動員により中国山脈の山腹を中心に横穴や壕を掘りました。その穴や壕は狙撃陣地や一人用の蛸壺、物資弾薬貯蔵庫などに使用する予定で鳥取県内で約560ヶ所ほどあったそうです。しかし、このことは秘匿作戦でもあったことから資料が残されているのはわずかで、のちの聞き取りなど調査によって判明したことが多いようです。その為、体験者個人の語りや伝聞により情報に差異があることはご承知おきくださいチ号演習に参加する町民は岩美駅から鳥取駅等の目的地に向かうため、朝の岩美駅は混雑しています。昭和20年7月30日早朝、グラマン戦闘機数機が岩美駅上空を飛来し、なんと機銃掃射をくわえ3人の死者が出てしまいました。岩美駅舎の看板にも記録されています。米艦戦機グラマン岩美駅襲撃の記録この日、和田さんも当番の日だったようですが、用事があったために集落の皆とは一緒に駅に行かず、別行動をとって5歳の息子さんと出発したそうです。場所は岩美駅より小高い山で500mほど離れたところ、すると、軽飛行機の音が鳴り、なにかと考える間もなく突然頭上で機銃の音が鳴り、近くの山にこだましてものすごい音が響き、自分が狙われいると思って慌てて逃げ隠れたそうです。また、岩美町の元小学校校長の永美喜雄先生の日記には七月三十日晴天、午前六時半過ぎ、編隊らしき飛行機の爆音を耳にするも警戒、警報の発令もない中での爆音だったのでたいして気に留めていなかったようですが、突然、けたたましい銃撃の音を聞き、瞬間的に敵機からの襲撃だと直感し裏庭に出ました。体調不良で寝ていた妻の静子さんも2階の窓から七機の飛行機が飛び去るのを見たそうです。早朝の汽車は通勤やチ号演習に向かう義勇隊の人々で混雑している中、大惨事には至らなかったとはいえ死傷者は数名、死亡者は線路工夫だった横町の男性、保線工夫詰所の焼失、等の被害を受けてしまいました。永美さんは自宅にいたため岩美駅にいたわけではないので細かい実情は知らないが、レールに銃撃の跡が残っていたという証言を聞いた記憶があることと但馬方面から鳥取に向かう方向に飛んでいたとの事をのちに記録していました。さらに福寿さんの記録では、死者3名、負傷者1名の犠牲者を出し、駅構造物(保線区詰所)、たまたま停車中の貨物列車に損害を与えたと残されています。この停止中の貨物列車と、プラットフォーム、詰所が並列に並んでいて、貨物列車の輸送活動を防止するための襲撃だったのではないかという憶測する人もいたそうです。犠牲者は岩美町出身の保線区2名、福部村出身の臨時女子職員1名で、保線区は即死、女子職員は両足に負傷をし岩井病院まで運ばれましたが助かりませんでした。自転車もほとんど見られない時代、リアカーのようなものも簡単に見つかったとは考えられない戦況下、おそらく搬送まで時間もかかったし現代と比べて医療器具も設備も不十分な状況だと想定されてます。負傷者は貨物列車の機関手で幸い、健全に生活を送ることができているらしく、この記録は実際に目にしたこと、犠牲者の親類がたまたま親しい隣人だったこと等から37年の時を越えて伝聞となったとしても正確に残っている記憶であるとの事です。福寿さんはこの時、岩美駅から200mほど離れた線路を歩いていたそうです(当時、自転車等が無い時代、東浜駅も大岩駅もなく、駅に向かう近道が線路だったことからみな線路を歩いて駅に向かっていたようです)相谷のなだらかな稜線を突っ切って急降下する数機の影が近づいてきたときに、『ああ、こんなところまでやってきたのか!!』と思いとっさに線路の土堤に伏すよう声を掛け合ったようです。チ号演習という正体不明の作業のために村に残っていた働き手はほとんど演習に動員されていたため線路は当然ながら混雑していたとの締めくくり。この締めは深く考えさせられますね。このことは誰が決めたでもなく米艦戦機グラマン岩美駅襲撃というようになったとのこと。※それぞれの記録にある・保線工夫・保線区は呼び方が違うだけで鉄道の線路を新設・増設したり、補修・保全したりする仕事に従事する人のことを指します。ちなみに、岩美町浦富出身の初代国連大使の澤田廉三さんの妻であるエリザベスサンダースホームの創始者である澤田美喜さんも岩美で疎開生活を送り塩づくりとチ号演習とおもわれる掘削作業に参加していたことを残されています。(手記にはトンネル掘りと記載、チ号演習の文字は無し)「ち号演習」に関する公文書は、戦時体制に関する公文書の焼却指令が発せられ忠実に実行したため情報がほぼ残っていない為、体験者の声というのは貴重だとおもいます。岩美駅が第二次世界大戦で襲撃があったことを知っている現代人はどれくらいいらっしゃるでしょうか?小さな田舎町の出来事、教科書に載ることもないでしょう。自転車も思うようにない中、負傷者を搬送すること自体に苦労し、医療器具も乏しく、食べ物も不足し…と頭を巡らせると胸がつまる思いになります。また、戦地に向かった町民もいて祖父、曾祖父、その兄弟、先祖、をたどると戦争を体験した身内や親類がいると思います。疎開地として都心部の子供たちを受け入れて少ない食糧をわけたり、衣服を与えたりと疎開してきた子どもたちの為に温かく迎え支援したことが、戦争遂行の手助けになり戦争を長期化させる行為だと判断されるという何とも切ないこともあったそうです。今の平和な時代だからこそ言えることなのかもしれませんが、不安な子供たちに愛情込めて親切にしたことが戦犯扱いになるのは理不尽すぎて悲しい!!!でも、、、、立ち位置によりごもっともな面もあり…でもでも子どもに罪は無いしみんな苦しい…支え合って生き延びたいのに…そんな中生き抜いてきた皆さま、命をつないできたこと大事に受け止めています。補足になりますが女優であり元参議院議長の扇千景さんは小学校4年生のとき、現在の神戸市長田区から鳥取県岩美町の岩井温泉の花屋旅館に疎開していたそうです。いつもご飯がわずかな大豆ごはん、おやつもわずかな煎り大豆ばかりでお腹を空かせてイナゴを食べたり、たまに大人からもらうおかきなどをみんなで分けた思い出、実家がなくなったことを聞かされたことを語られています。終戦日の事故のはなし朝鮮の元山から小松基地に向かう海軍96式陸攻7人(高知県出身者が操縦)が浦富海岸に不時着し、幸い全員に大きなけがはなく、暗闇の中、岩美駅まで歩いて汽車を待ったそうです。 いわみのあしあとでは岩美町から戦地に向かった人の体験談、戦地に向かった子供・夫・父を待っていた家族の事なども記録したいと思います。ちなみに公文書館発行の新鳥取県史【孫や子に伝えたい戦争体験】を購読しました。戦地の方や、鳥取で待つ家族、戦時中戦後の暮らしなど鳥取県出身者の方の手記を読むことができます。
-
サイパン島で出会った岩美町Tさんの記録鳥取県公文書館から入手した『孫や子に伝えたい戦争体験』上巻に、鳥取市のMさんの手記が掲載されていました。Mさんは昭和19年5月に海軍陸戦隊としてサイパン島に上陸されました。そこで岩美町のTさんとの敗残兵ともいう生活を迫真の思いで書かれています。サイパン島は食糧も水もなく身体が衰弱する中、ジャングルで隠れながら身を守り、とても苛酷な戦地でした。『孫や子に伝えたい戦争体験』詳細と購入できる場所一覧(鳥取県HP)ネット通販での購入はこちら(とっとり電子申請サービス)その前にサイパン島での出来事について要約します。日本は1942年前半まで太平洋戦線で連戦連勝し、広大な支配領域を築いていました。しかし、ミッドウェー海戦やガダルカナル島の敗北を経て、戦局は逆転。1943年、日本は防衛ラインを後退させ「絶対国防圏」を設定。その中核がサイパン島でした。サイパンは日本本土への空襲が可能な距離にあり、アメリカにとって戦略的拠点になるため日本はサイパンを死守すべき「絶対国防圏」の要と位置づけ、守備隊を強化しました。1944年6月15日、アメリカ軍がサイパン島に上陸。日本側は防衛体制が不十分で、司令官の小畑英良中将も不在という混乱の中で戦闘開始、一部のベテラン部隊が善戦し、アメリカ軍に大きな損害を与えるも、物量と兵器の差は圧倒的でした。日本軍は戦車による夜襲などで反撃を試みましたが、バズーカ砲など最新兵器により壊滅しました。日本軍は7月7日バンザイ突撃をし、アメリカ軍はそれを恐怖に思いながらも撃破、翌7月8日より北端に向かって掃討作戦を開始、7月9日に日本軍は事実上全滅。司令官斎藤義次中将らも自決。多くの民間人も「生きて虜囚の辱めを受けず」として自決を選び、アメリカ軍の説得も聞かず悲劇的な結末になりました。その自決の地でもあったのがのちに、スーサイドクリフやバンザイクリフ(岬)と呼ばれる断崖絶壁。ここに何人もの民間人が飛び降りたのです。サイパン陥落により、日本本土への空襲が本格化し戦局はさらに悪化しました。このサイパン島での戦いは、日本にとって「絶対国防圏」の崩壊を意味し、戦争の転機となりました。民間人を巻き込んだ悲劇性も含め、今なお深い記憶として語り継がれています。孫や子に伝えたい戦争体験内では本名が書かれています、もしこのTさんにお心当たりがある場合、鳥取県公文書館に連絡されると知りたいことが知れたり、何かの解決につながるかもしれません。『孫や子に伝えたい戦争体験』詳細と購入できる場所一覧(鳥取県HP)ネット通販での購入はこちら(とっとり電子申請サービス)サイパン島のャングルの中を追われる日々7月9日からは敗残兵としてジャングルの中を追われる日々でした。5ヶ月経った昭和19年12月頃、鳥取市のMさんはバンザイクリフまで追い詰められた際、民間人も軍人も一緒になって行動しる状態となっていて、子供と一緒に飛び降りする母親や、自決する軍人もいて絶体絶命状態でした。この時に、岩美町出身のTさんと一緒で、海中に飛び込むことを諦め、岩伝いに海に降りる場所を偶然見つけ、そこを降りるとなんと!樽が漂着していたらしく、その樽に身に着けていたゲートルを巻き付けて、2人で沖へ泳いだそうです。約2時間ほど泳いだところ、敵も陣地に帰った様子だったので島に戻ることができましたが、その後、身を潜めたジャングルが敵の陣地だったようで襲撃され、その時に鳥取市のMさんと岩美町のTさんは別れてしまったようです。その後、岩美町のTさんには会うことができず、昭和20年5月頃に収容されたMさんはしばし苛酷な労働をし、帰国の後、岩美郡に行き、あちこち訊ねたけどTさんの情報は全く得られず、もしかすると、あの樽で泳いで戻った時の襲撃で倒れたのではないかと思うとTさんの最後を見届けられなかったことが悔やまれてならない、っと言葉を残しています。体験記を読んでいると胸がつまる思いがします。飢餓や伝染病、栄養失調、睡眠不足に恐怖心の戦地での日々を思い出すと苦しい、悔いが残る仲間との別れ、憤り、また、戦地で戦うだけでなく、医療活動、建築土木作業、営繕や配給係など様々な役割をされた人、日本で待つ家族、製造をする人たち、岩美町からもたくさんの先代が未来に生きる家族、血はつながらずとも同じ日本で生きる私たちの為に魂を尽くしたこと胸に刻み、平和を維持し、毎日を大切に生きねばと強く思います。新鳥取県史【孫や子に伝えたい戦争体験】を購読しました。戦地の方や、鳥取で待つ家族、戦時中戦後の暮らしなど鳥取県出身者の方の手記を読むことができます。⇒ 孫や子に伝えたい戦争体験の内容について
-
鳥取県民の戦時中の暮らしを知ろう1945年8月15日に第二次世界大戦(太平洋戦争)が終戦しました。鳥取県・岩美町でも戦争の影響があり、出征、勤労動員、学徒動員、軍国少年団、挺身隊、チ号演習とグラマン戦闘機の岩美駅襲撃など国民一丸となり戦争を経験した歴史があります。孫や子に伝えたい戦争体験(書籍)によると、上巻では戦場体験、シベリア抑留、大陸からの引き揚げ、満州開拓団、青少年義勇軍としての体験談、下巻では鳥取県で過ごす戦時中、勤労動員の体験、国民学校の思い出、空襲や被爆、事故や事件など個人の手記が掲載されています。岩美町出身の初代国連大使の澤田廉三さんの妻である澤田美喜さんの疎開生活でのチ号演習ともリンクすることもあり、複数の方の体験談を読んでいくと繋がりが見え、よりいっそう理解することができます。勤労動員・学徒動員・軍国少年団学生ながら勤労動員として呉や舞鶴へ海軍工廠として戦艦、潜水艦、小戦闘機、魚雷の制作や電気系統の修理や保守を行ったり、鳥取県内では体力検定として千代川の西から河原の国民学校まで砂袋を背負って22㎞の行軍競争をしたり、雪の浜坂から鳥取砂丘を歩く訓練をしたり、食糧増産隊として校庭や空地の開墾、食物の栽培等を行いました。また、小学校の子供(手記によると当時8歳のケースもあり)でも夏休みもなく、学校の授業も減り、特攻の練習場でもある湖山飛行場や道路の整備作業でローラーを引いたり、ススキの穂を採取して兵隊さんの浮袋の材料や、軍馬の飼料にしたり、イナゴを捕獲して兵隊さんのたんぱく質という栄養食糧を採取する日々だったようです。鳥取に居ながらにして軍国少年団の子供たちも兵隊さんたちの為に!と長距離歩いたり川を越えてススキや松根油の採取に精を出し、松の根が採取出来ないと帰れないので、苦労して掘り起こした時には担任の先生とクラスメイトで喜びの声を挙げたり、兵隊さんの為の防寒帽を作るために兎の皮を採取することもあったようです。松根油は飛行の燃料に使えるとして採取されましたが大規模な実用化にはならなかったようです家族を待つ女性や挺身隊鳥取で父や夫、兄弟や子供を戦地に見送る女性たちの暮らしは、出征により人手不足となった地域の農家さんの果樹栽培や稲刈り作業、芋などの穀物栽培を、時には牛や馬を使いながら力仕事もこなし、男性不在を補っていました。東京や大阪で空襲に遭った人たちが鳥取駅に溢れている頃、兵隊さんのお見送りや遺骨の出迎えなどをし千人針、慰安袋の作成、出征家族の安全祈願の寺社参り、こどもと同様、イナゴなど食材採集、塩づくり、チ号演習のための掘削作業に勤しみました。また、挺身隊として兵庫県の方の縫製など軍需工場で労働するひともいて、空襲警報で1日に何度も防空壕に避難するために仕事が1-2時間しかできない日などもあったようです。また花嫁修業といういわゆる無職状態だと挺身隊に招集されるため、それを避けるために地元で教師や事務職など就職をする女性が増え、戦争が終わるころには男性教師も戦地に出ていたためほぼ女性教師だった学校もあるようです。昭和18年には鳥取地震もあり、復興のための物資も思うようになく、戦地に送るものも、自分たちの日々の必需品もどんどん足りなくなり苦労を重ねたことは大いに想像できますね。書籍によるとこどもの内からお国のためにと身体を酷使して働き栄養のある食事をとることもなかなかできない中、皆で協力し合って日本を守っていたこと、暴力がある教育やしつけ、終戦で無気力になってしまったこと、その後の教育がガラッと変わってしまったこと、女性が一生懸命男性不在の中で働いてきたこと、戦争という渦の中で葛藤してきたことなどを手記で読むと、様々な思いが巡ります。鳥取県編・孫や子に伝えたい戦争体験2025年の段階で、第二次世界大戦(太平洋戦争・大東亜戦争)が終戦して80年になります。戦争の記憶が鮮明にある方はおよそ85歳以上の方になりますので、だんだんリアルな声を聞くことができなくなります。戦争時の生活、戦地での体験は思い起こすことが苦しい人、命を落とした仲間を想うと自分は生きてていいのかと激しく自責の念を持つ人、話したくない人、話せない人、戦争が無い今、知る必要が無いと口を閉ざす人もいらっしゃるのも承知です。その中で貴重な体験談を時を重ねて告白してくださったこと、それを引き継いでいくことが大切だと思います。鳥取県立公文書館・鳥取県にて発行されている鳥取県編・孫や子に伝えたい戦争体験、是非お読みください『孫や子に伝えたい戦争体験』詳細と購入できる場所一覧(鳥取県HP)ネット通販での購入はこちら(とっとり電子申請サービス)
-
和田麻太郎さんの功績を知ろう!鳥取県岩美郡岩美町浦富出身の和田麻太郎さんは、明治44年2月に浦富竹本家の三男として生まれ、東京や大阪で商売をしながら太平洋戦争前後を生き抜き、晩年は東京・国立で家具製造会社を営んでいた郷土愛のあふれる日ソ親善の功労者です。和田さんは尋常高等小学校を卒業後、1914年(大正3年)の14歳の時に姉を頼って大阪で仕事をし、様々な経験を積みました。大阪、神戸、尼崎にあった工場を親類に任せ1941年(昭和16年)には岩美町に帰ってきて浦富の立町で数年前から兄に任せていた製材工場とは別で木材商を営みはじめました。しかし、良材は軍の公用材として提出させられ、支払いもいつになるかわからない上に、残材も自由に売ることができず不安定な状況になり、意を決して17年には東京に移住し戦争前後の苦難の中、梱包用木箱の製造工場、空き瓶買い、など目の前のできる事をビジネスに変えて新店舗を借りた矢先、赤紙令状がとどきました。作ったばかりのお店を閉じ、岩美町の先祖の墓参りを済ませて岩美駅で見送られ、姫路の第十師団に入営しましたが、その日の身体検査で視力不足で即日除隊になったのです。除隊になったその足で、また東京への夜行に乗って店舗再開のために物件探しをはじめました。防空用品の販売等が軌道に乗りましたがグレーな部分もあり閉店に追い込まれます。その後、戦時中は何度も何度も空襲から危機一髪で逃れながら夜光マークといって胸に縫い付ける名前と血液型を記載する蛍光塗料を塗った名札布や骨折時などの添木、ゴム製の止血帯、火たたき、列車の窓等に使う金属の引き手が金属回収のために木製にする代用品の製造販売など行っていました。そのことについては和田麻太郎さんの手記に記載されています。浦富に帰ってからは生活のために田畑を耕し、町会単位で塩づくりをしたり『ち』号作戦の作業をして過ごしていました。「ち号作戦」(チ号作戦・演習)は、太平洋戦争末期に日本陸海軍が実施した秘匿作戦の一つで、この作戦は、敵の九州上陸を想定し、沿岸防御のための築城作業を行うものでした。具体的には、中国山脈の山腹を中心に狙撃陣地や物資弾薬貯蔵庫などを掘る作業が行われ、岩美町もその対象でした。この作戦は昭和20年5月7日から始まり、県内各地で約560の横穴や壕が掘られ、作業には多くの人々が動員され、賃金は未払いのまま終戦を迎えました。(澤田美喜さんの履歴書にも、浦富に疎開しているときに、穴を掘りに行っていたと記されているので、この『ち号作戦』だったのではないかと思います。)その時に、グラマン岩美駅襲撃が発生します。7月30日、和田さんもち号演習の当番だったのですが、他の都合があって別行動をとっていたために難を逃れましたが襲撃の音を聞き、現場にも駆けつけてリアルな証言を残されています。終戦後また上京をし家族を持ち一生懸命働き続けました。チ号演習とグラマン戦闘機の岩美駅襲撃に記載歳を重ねるにつれ岩美町への郷愁は募るばかりで毎年里帰りをしては知人と集まり、岩美町に何が必要か?を談義していました。岩美町にサクラやアジサイなどの花を贈ったり浦富小学校に本を進呈したりと、都心部で会社の経営をしながら常に岩美町のことを考えて支援をしていました。戦後昭和27.8年ごろ、日米関係が深まるにつれ、ソ連とも交流しなければ…と思いつき、ソ連大使館を日参し、当初は子供同士で絵の交換などができないか?など考えていたそうです。なかなか思うようにいかず、時が流れて昭和62年の事、とても大きな功績を遺したのが同じく浦富出身の初代国連大使の澤田廉三さんが建立した露軍将校遺体漂着記念碑を全国に知らせることと、ソ連(現ロシア)との友好関係を結ぶための立役者になりました。そのことは別のページで詳しく記載していますので併せてごらんください。露軍将校遺体漂着記念碑について和田麻太郎さんの晩年和田さんは岩美町浦富出身で浦富小学校(平成7年3月廃校⇒岩美北小学校)が母校です。故郷を思う気持ちで20年間以上、町や学校に桜の苗木を贈り続け、浦富小学校には【和田文庫】と称した、児童図書のプレゼントが並んだ一角があったそうです。和田さんが岩美町に贈った桜は桐山のいわし山鳥取池田家家老・鵜殿家の墓地金峯神社のある金峯山岩美駅周辺に植えられました。 (当時の浜浦富老人会の役員さん談)1989年の78歳の時に闘病中だと知った浦富小学校は生徒を中心に和田さんへ千羽鶴と共に『わだのおじいちゃん、早く病気を治して元気になってください!』と励ましの手紙を贈り、受け取った病床では娘さんに何度も手紙を読みあげてもらっては嬉しそうにしていたようです。また露軍将校遺体漂着記念碑を通じて、日ソ友好親善に尽力したことから1989年6月、日本対外文化協会から感謝状を贈呈されました。周りから励まされながら1989年7月4日、胃がんのため生涯を閉じましたが贈った桜の生命は続き、図書も読まれ、和田さんの功績や意志は語り継がれています。