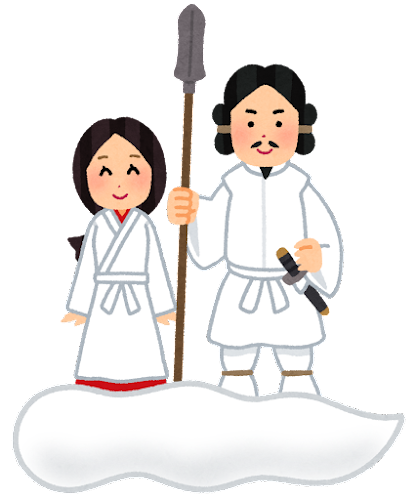勧学寺の歴史を知ろう
鳥取県岩美町の羽尾海岸にある山陰海岸ジオパークトレイルの羽尾岬コースの入り口(昭和民宿龍神荘さん横)に位置する勧学寺は、因幡観音霊場の第九番札所として知られています。本尊は二尺五寸の十一面観音菩薩で、行基によって作られた(寄木嶋にかかりたる霊木にて刻む)と伝えられています。この観音像は、霊験あらたかで多くの信仰を集めてきました。脇士は広目天王、多聞天王です。
勧学寺の歴史は古く、かつては天台宗清境寺(比叡山延暦寺)一山十二坊の一つでした。行基が開山したのち、約300年前の元禄3年、中興庵主である浄霊坊は但馬往来の通過点の細川村に浄霊橋を架け、往来の煩いを取り除きました。寛延2年(1749年)3月3日には別当龍泉院として縁起を改めて開帳、
しかし、明治3年(1870年)11月に維持困難になり一時廃寺となりこの頃は大霊院末観音寺と称しました。その後、明治30年(1897年)7月、大霊院住職智光阿闍梨(仏教の位の高い僧侶や僧侶の資格を持つ者)の力により再建、現在の場所に移転されました。
境内からは羽尾海岸の砂浜が一望でき、向こう岸は陸上岬と東浜海岸で海水浴シーズンには海水浴、年間通して波乗りが楽しめます。周辺には山陰海岸最大級の海食洞「龍神洞」などの自然景観もあり、この地域は、自然と歴史が融合した魅力的な場所です。
〒681-0014 鳥取県岩美郡岩美町大羽尾267
語句の補足
大羽尾の十一面観音菩薩と祭りについて
村民の山口義則さんが観音様の功徳を世の中に広めていきたいという思いを語った記録によると、

但馬の人から大羽尾には十一面観音様というあらかたなお寺様がおられるといった話が伝わっていることを知り、村民として大変うれしく思いました。
戦争中には、浜辺はもとより、遠くの人々も多く参詣に来ておられ、いろいろ武運をお願いしに来られていた様子でした。昔の人の話では、漁に出て荒れてきたときなど心配な時には家族のものが船がどうなっているかを尋ねてきて
『東におる船はまだ陸についていないけど安心せよ』『西に当たる船は、やがて便りがあるだろう』
と導かれ大変によく当たったという事です。私たちの先祖は、本当に観音様のおかげで安心して生活をつづけてきたとおもいます。
十一面観音の真言は【オンロケイジンバラ キリクソワカ】でそれぞれの梵字(サンスクリット語)の意味は唵(おん:帰命・帰依)嚕鶏(ろけい:世間)入縛羅(じばら:光明)紇哩(きり:蓮華部を象徴する種子)、娑縛訶(そわか: 成就や祈願の意)とし、直訳は「おお、世の中を照らす者よ」だそうです。
つづいて

ただ、狸(狐)が悪事を働いて人に憑いて困らせた話を聞いています。
とのこと…これは岩美の伝承話に記載します。
話を戻して大羽尾の御本尊様は、東向きに安置されています。
大羽尾の部落行事には『観音様』に関するものが多く、三夜さんの行事は1月23日、5月23日、9月23日の3回で特に5月23日の三夜さんには青年たちが観音堂に参籠し、『南無大悲観世音菩薩』と唱えて33度礼拝をし、真言【オンロケイジンバラ キリクソワカ】を唱して、心願の成就を祈り、庫裡(くり:寺院の台所や僧侶が居住する場所)で日の出まで酒宴をしてにぎやかでした。
旧暦6月の17日観音祭りでは18日にかけての本尊観世音菩薩の例祭で、クジで本番・後番を定めて各々に本尊の分霊御幣を受け、僧侶は午後当番のお宅に祈念に出張します。夜は本堂尊前で護摩修行大祈祷が執行され、12時頃まで参詣者が続きます。18日は、前日に引き続き観音様の祭礼、午後5時頃より分霊の御幣を本堂に変遷する祭事があり、再度、『天下泰平・風雨順時・五穀豊穣・家内安全・心願成就』の護摩修行が執行されます
また7月の盆行事の最終日の17日には観音祭と称し、青年たちが主体となって33度祈念のあと、浜で盆供養の踊りをしました。
33という数は、観音菩薩が衆生を救うとき33の姿に変化するという信仰に由来しています。