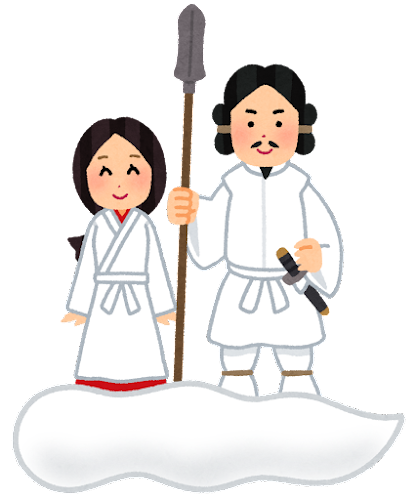岩美町の修験場 荒金業者山について記載します岩美町には修験道の霊場として、役行者(えんのぎょうじゃ)によって神仏混合の業場が開かれたとされる行者山があり【因幡の国が峰】といわれており、資料には山ノ神、弁財天が鎮座していると記されていました。4月3日と7月7日(近年は7月の第一日曜日)が業者山の祭事で集落の入り口に幟旗(のぼり)を立て、公民館医役行者像を掛けてお経や御詠歌をあげています。荒金集落には業者山への入り口を示す鳥居があり、その鳥居3㎞奥の業者山登山口には弁天堂があります。山頂へ登る道は銚子口、犬戻し・犬返しと呼ばれるほど険しく危険な箇所があり、以前は単独でキノコ採りなどで入山した外部の方の滑落事故や、遭難などがあり、地元の方は単独で入山することを推奨していません。また崩落個所も多く、足元も砂地で滑りやすいところや勾配もきつく、年に一度行われる地域の方とともに登山道整備を行った時の写真を最後に追記します。行者山の登山道整備年に一度の整備を兼ねた登山に仲間が参加させていただくことになり草刈り道具を持ち寄り、案内してくださる地元の方や役場の職員さんなど20名ほどで険しい修験道を登りながら道を整備した際の写真です。最後の写真は下山後に荒金コミュニティーの展示物で荒金鉱山についても改めて学びました。また石標や一丁地蔵も残され、山頂の岩窟内には行者堂と大日堂があり、元禄14年(1701年)銘を持つ役行者像や棟札などが残されています。三徳山投入堂に行った際の写真を掲載しているので併せてごらんください荒金行者山と関連あるスポット荒金行者山は伯爵大山、三徳山に続く修験場で、荒金行者山に続き、牛ヶ峰山、金峯山が最終とされています。また荒金鉱山も見学でき、写真を掲載していますので併せてご確認ください。
いわみのあしあと・歴史と観光と暮らしの記録
「 岩美町 神社 」の検索結果
-
-
網代神社にお参りに行こう!鳥取県岩美町網代に鎮座する網代神社は、網代漁港、鳥取砂丘を望む境内からの絶景が地元の方だけでなく観光客からも人気のスポットです。 またお祷祭では日本遺産でもある麒麟獅子が1軒1軒舞う伝統行事が行われます。創立年代不明ですが、因幡誌によると石見の国(現島根県)の漁師が日比屋(大谷村)に流れ着いたのちに網代地区に移住したことにより、1573~92年(天正)の間、氏神であった八幡宮を勧請し、現在地に移り変わったとされています。1763年(宝暦13年)に社殿を造営し、祭神である誉田別命(ほんだわけのみこと)は大漁旗を意味する海神である八幡神(やはたのかみ)としても知られていて、八幡宮から明治時代に網代神社に改称されました。例祭日:旧8月15日(10月15日)お祷祭:(麒麟獅子)春4月15日に近い土曜・日曜 秋9月14・15日祭神:誉田別命(ほんだわけのみこと)/応神天皇(仲哀天皇と神功皇后の子)/守護(国家鎮護)神、武運長久、学問成就、国家鎮護、豊穣祈願、 病気平癒、安産・子育・子宝の神様、水神100段を超える石段を登る境内には祭神である応神天皇の親でもある若宮(神功皇后:気長足姫命(おきながたらしひめ)子育大願、 安産祈願)も祀られ、参道途中の恵比寿社に(事代主命:ことしろぬしのみこと:大国主命の子、天皇を守護する託宣の神)も祀られています。※恵比寿神(えびす)が事代主神と同一視されることも多く商売繁盛や海の安全や豊漁を願う神とされ、網代地区は漁港なのでこの信仰が厚いのではないかと思われます。所在地:岩美町大字網代140
-
愛宕神社(愛宕山展望台)を知っておまいりに行こう!鳥取県岩美町岩井の愛宕山頂に鎮座する愛宕神社は将軍地蔵菩薩石像が祀られていて火伏せ・防火を意味しています。岩井集落を望む山頂にはゆかむりの塔があり、岩美町出身の山本兼文さんの作品です。頂上までの山道は比較的緩やかで30分程で下山できますが、時期によってはシカやイノシシがいた形跡があるので気を付けてください。愛宕山神社の周辺をまち歩きしよう愛宕山神社が鎮座する愛宕山登山や岩井温泉集落など周辺のまち歩きも学びが沢山あります岩井温泉集落〜旧岩井小学校〜愛宕山頂上〜ゆかむりの塔〜愛宕山神社愛宕神社(愛宕山展望台)元岩井小学校校舎(町指定文化財)岩井温泉岩井廃寺塔跡(国史跡)御湯神社木島よし
-
荒金神社にお参りに行こう!鳥取県岩美町荒金にある荒金神社は、山深い場所にあり、勾配のある階段を上った先の木々に囲まれた場所にあります。参道までの広場では春に桜の花が綺麗に咲き、古くは熊野権現を氏神としていましたが、明治初年に熊野神社の分霊を奉じ、村内の末社を合祭して独立しました。荒金神社の歴史は古く、『因幡誌』などの文献にも記されています。また、荒金村は古来より「荒金」という名前で知られており、和銅年間(710年頃)に元明天皇に銅を献上した際に「荒金」と命名されたという記録もあります。もとは荒金銅山にありましたが銅山が閉山したのちに現在地になりました。神社の例祭は毎年3月28日に行われ、子供神輿の榊行事などが行われています例祭日:3月28日祭神:素盞嗚命 (すさのおのみこと:伊邪那岐命の子で天照大神の弟)/災害や疫病の厄除け、縁結び、安産・子育て、心身の成長や成熟、心身健全、技芸上達、 夫婦円満所在地:鳥取県岩美郡岩美町荒金724荒金神社付近には荒金行者山・荒金鉱山、荒金鉱山犠牲者慰霊碑などの歴史スポットほか、天地有氣・荒金さんというカフェもあります。
-
稲荷神社におまいりに行こう!鳥取県岩美町外邑(とのむら)地区にある稲荷神社は伏見稲荷大社より勧請した稲荷大明神とされた氏神で棟札には1705年に建立したという記録があります。明治初年に高谷にあった大歳大明神(おおとしがみ/素戔嗚尊の子で、豊穣をもたらす神様)を合祀して、稲荷神社と改称しました。趣ある鳥居をくぐって石段(手すりあり)を登った先にある拝殿には立派な彫刻が施されています。祭神は五穀をつかさどる神で、まさに地域の暮らしの安全と発展を護るために祈願されていることが伺われます。例祭日:4月23日・夏祭7月23日祭神:倉稲魂命(うかのみたまのみこと)/五穀豊穣・商売繁盛の神様稚産魂命 (わかむすびのみこと・ わくむすびのみこと ) 別名・宇迦御魂神(うかのみたまのかみ)/養蚕や生成発展、縁結びの神様余談ですが…倉稲魂命は日本書紀では伊奘諾尊と伊奘冉尊の子とされ、古事記では須佐之男命と神大市比売命の子とされています所在地:鳥取県岩美郡岩美町外邑594
-
宇治神社におまいりにいこう!鳥取県岩美町大字宇治に位置する宇治神社は、創立年代は不詳ですが、中世には石清水八幡宮の荘園であった宇治庄にありました。時は平安時代、京都の山城宇治に住んでいた藤原冬久(藤原冬嗣(775-826)公卿(くぎょう)の子孫)が皮膚病を憂いて旅に出た際に立ち寄った岩井で巫女の導きのまま温泉を掘り起こし、湯に浸ると皮膚病が回復したことからそのまま住みつき、岩井温泉を開湯し、その地の名を出身地である宇治と称し、宇治長者となったという歴史があります。その宇治地区の山すその参道の急な石段を上った先にあるのが宇治神社。境内からは国道9号線が良く望めます。1660年(万治3年)に社殿が造営され、近世まで八幡宮と称されていて、明治初年に宇治神社と改称され、大正6年に周囲の神社は御湯神社に合併しましたたが、宇治神社は合併せず現在に至っています。また長安寺とも敷地がつながっています。長安寺・垣屋恒総の宝篋印塔(町史跡)例祭日:4月15日、例祭前日には全戸が公民館に集まりお祷祭を行い、例祭当日は神社で祭典が行われ、その後獅子舞が各家を回るという伝統があります祭神:誉田別命(ほんだわけのみこと)/応神天皇(仲哀天皇と神功皇后の子)/守護(国家鎮護)神、武運長久、学問成就、国家鎮護、豊穣祈願、 病気平癒、安産・子育・子宝の神様、水神所在地:鳥取県岩美郡岩美町宇治609神社背後の山には中世、山名家が守護国の際、安藤采女正の居城であった下香谷城跡があります。岩井温泉に関する記事もお読みください岩井温泉明石家(岩井温泉)岩井屋(岩井温泉)木島よし
-
大坂神社におまいりに行こう!鳥取県岩美町の大坂にある大坂神社は岩美町南端の山の中にある彫刻が特徴的な神社で祭神は猿田彦命と大山祇命です。創立年代は不詳ですが、棟札に「享保元年(1716年)明奉建立白髭大明神神殿一宇九月二十九日」と記されていて近世では白髭大明神と称されていました。明治初年には境内末社の山ノ神(大山祇命)を合祀し、大坂神社と改称され現在も例祭は毎年3月26日に行われています。6月には個人宅にて代満祭が行われます。代満祭(しろみて)とは、田植えが終了したことを田の神に報告し、共に祝う農家の行事です。例祭日:3月26日・6月に代満祭(しろみてさい)祭神:猿田彦命(さるたひこのおおかみ)/物事を良い方向へ導く「みちひらき」の神様・交通安全、方位除け、五穀豊穣、事業開運、人生開運、縁結び、夫婦円満、所願成就、 芸能大山祇命(おおやまつみのかみ)伊邪那岐命と伊邪那美命の子/山岳丘陵の守護神、水源・水利の神猿田彦命は天照大神の孫である瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を地上に道案内した神といわれています。所在地: 鳥取県岩美郡岩美町大坂22大坂神社付近の37号線を北西に進むと岩美町立町民いこいの里があります。
-
大羽尾海岸におまいりに行こう!大羽尾神社は、鳥取県岩美町大羽尾に位置する神社でおおばにょうと呼びます。神社の起源は明確には分かっていませんが、古老の伝承によると、奥谷市郎右衛門という人物がこの地に来て、武神である武甕槌命を勧請し、一社を創設したとされています。近世には「無言大明神」または「武王大明神」と呼ばれていましたが、明治初年に「大羽尾神社」と改称されました。祭神は武甕槌命で、例祭は4月16日、灘祭は旧5月5日(現在は6月5日を過ぎた土曜日)、寅祭(秋祭)は11月の寅の日に行われています。また、重要無形文化財に指定された因幡の菖蒲綱引きもおこなわれていました。(※平成25年から少子化により余儀なく休止しています)神社は集落の中心の山腹に東北に面して鎮座しており、石段を登った先にある境内からは美しい羽尾海岸が望めます。境内には稲荷社・子持御前社・恵毘須社(港)・龍神社・金比羅社・天満宮があり、商売繁盛や大漁満足、航海安全や学業成就など、漁港で暮らす人々の心を支えています。社叢にはタブノキやヤブツバキが優先種として生育しており、参道脇には直径25センチメートルのオオバグミの老木があります。例祭日:4月16日灘祭・旧5月5日(現在は6月5日を過ぎた土曜日)寅祭(秋祭)・11月の寅の日祭神:武甕槌命(たけみかづちのみこと)雷神/勝利、縁結び、安産、国家の平和と繁栄所在地:鳥取県岩美郡岩美町大羽尾419−1大羽尾にまつわる伝承話羽尾の狸(狐)にまつわる話では大羽尾神社のお稲荷さんの話もありますのでご覧ください
-
岡森神社におまいりに行こう!鳥取県岩美町長谷に位置する岡森神社は祭神は興登魂命、大山祇命、岐神で神社の由緒は不詳ですが、棟札によると「岡森大明神建立成就享保三暦(1718)」と記されています。石垣がある境内は木々に囲まれ静寂さを感じます。明治初年に大山神社と岐神(くなどのかみ)を祀る神社を合祀し岡森神社と改称され、大正6年に御湯神社に合併されましたが、昭和24年に再び分離され、本殿、幣殿、拝殿を再建し、遷座して復興しました。神社の例祭は毎年10月3日に行われ、春祭は4月3日に行われます。春祭では獅子舞や榊、子供の屋台が集落内を巡回します例祭日:10月3日祭神:興登魂命(おきとだまのみこと)天児屋命(あめのこやねのみこと)とも呼ばれ中臣氏と藤原氏の祖神/国家安泰、学業成就、出世開運大山祇命(おおやまつみのかみ:伊邪那岐命と伊邪那美命の子)/山岳丘陵の守護神、水源・水利の神岐神(ふなど・くなどのかみ)/牛馬守護の神、豊穣の神・禊、魔除け、厄除け、道中安全の神岐神(ふなど・くなどのかみ)は、道の分岐点や峠、村境などに祀られる道祖神で、邪霊の侵入を防ぎ旅人を守ると信じられています。所在地:岩美町大字長谷439クナドは「来るなという入り口」の意で外からの外敵や悪霊の侵入をふせぐ神とされていますが、陸上や網代、新井などにある地域にゆかりのある力士の名を石に彫り、集落の入り口に置いて外敵から守る意味を持つ相撲塚も似た意味を持ち合わせているのかなと思いました。
-
恩志呂神社におまいりしよう恩志呂神社(おしろのじんじゃ・おしろじんじゃ)は鳥取県岩美町恩地(おんぢ)集落にあります。背後の山には上ノ山城跡があり、この地域は中世には岩山城址・猪尾山城跡など、城が多く存在していたことがわかっています。こう配の石階段を登った先にある境内・広場からは岩井集落が望めます。この神社は、天武天皇の時代(白鳳4年、676年)に奉幣勅使が下向した記録があり、その時に本使や副使が神社に参拝し、金銭を奉納したと伝えられています。また、恩志呂神社は『延喜式』神名帳(927年)にも記載されており、その由緒は非常に古いものです。恩志呂神社の例祭は4月9日に行われ、夏越大祓(夏祭)は旧暦6月9日前後の日曜日、秋祭は旧暦9月9日前後の日曜日に行われ、例祭では麒麟獅子舞が全戸を巡るという伝統があります例祭日:4月9日夏越大祓(夏祭)…旧暦6月9日前後の日曜日秋祭…旧暦9月9日祭神:火闌降命(ほのすそりのみこと)ににぎのみこととさきやこのはなひめの子/火の神様大山祇命(おおやまつみのかみ)伊邪那岐命と伊邪那美命の子/山岳丘陵の守護神、水源・水利の神天津日高日子番能迩迩藝能命(あまつひこひこほのににぎのみこと)/五穀豊穣や商売繁盛、国家安寧、殖産振興木花開耶姫命このはなのさくやびめ)大山祇命(おおやまつみのかみ)の子であり天孫瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の妻/火難除け、安産・子授け・縁結び火明玉命(ほあかりのみこと)ににぎのみことの子であり天照大神の孫/太陽神・農業神所在地:鳥取県岩美郡岩美町恩志85
-
小田神社におまいりに行こう!鳥取県岩美町大字小田に位置する小田神社は姥ヶ山の南の麓にある村社で鳥居をくぐり石段を80段ほど上がる小高い場所で春には桜が綺麗に開花します。祭神は大山祇命と木花開耶姫命で、神社の由緒によると、貞享4年(1687年)に創立されたとされ、天明8年(1782年)には「大神山神」という棟札が残されています。石鳥居は弘化3年(1846)に疫病が流行り、疫病退散祈願に建立され、山の神と称されていました。明治初年に小田神社と改称され、地元の産土神として信仰を集め、現在も例祭は毎年4月10日に行われ、獅子舞の奉納などが行われています例祭日:4月10日祭神:大山祇命(おおやまつみのかみ)伊邪那岐命と伊邪那美命の子/山岳丘陵の守護神、水源・水利の神木花開耶姫命(このはなのさくやびめ)大山祇命(おおやまつみのかみ)の子であり天孫瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の妻/火難除け、安産・子授け・縁結びのほか、農業、漁業、織物業、酒造業、海上安全・航海安全など所在地:岩美町大字小田206ちなみに、小田ノ大谷は延興寺の鐘撞大明神も氏神(産土神)とされていたようです。小田集落の37号線を北に戻るとたきさん温泉、東に進むとキャンプ場の岩美町立町民いこいの里があります。
-
唐川神社におまいりに行こう!唐川神社は鳥取県岩美町に位置する神社で、歴史は古く、由緒ある場所です。神社の創建は明らかではありませんが、近世まで同地に大神宮(延享4年(1747)の棟札が現存)と山ノ神(安永8年(1779)の棟札が現存)の二神を奉斎していたことから大神宮として信仰されていたことが分かります。明治元年にこれら二神を合祭し、唐川社と称し、後に唐川神社と改称されました。祭神は天照大神と大山祇命で、例祭は4月11日、夏祭りは7月11日に行われています。集落の東の山裾に南面して鎮座していて、木製の古い鳥居をくぐると、手すり無しの苔の石段があり足元に注意が必要です。登った先にある神社の境内は竹などの樹木に囲まれています。この唐川神社は地域の歴史と深く結びついており、地元の人々によって大切にされています。例祭日:4月11日・夏祭り・7月11日祭神:天照大神(あまてらすおおみかみ)/太陽神、天皇家の祖先神大山祇命(おおやまつみのかみ)伊弉諾(いざなぎ)尊・伊弉冉(いざなみ)尊の子/山岳丘陵の守護神・水源水利・商売繁盛・家内安全・長寿・良縁・安産所在地:岩美町大字唐川76唐川地区は国の天然記念物指定のカキツバタ群落がありますので5月下旬から6月初旬の見頃に足をお運びください。
-
甘露神社をしっておまいりにいこう!線路沿いから約90度曲がり鳥居をくぐると一気に静けさが増し,県内では珍しいシダ植物が生育している参道、岩壁からにじみ出る水と苔も美しいです。甘露神社は852年(仁寿2年)5月に創祀と伝わり、現在地より西へ約1キロほど先にある通称神谷山にありましたが、中古、戦乱により、海賊が侵攻し放火や泥棒など治安が悪くなり村民が離散して神事執行ができなくなったため、現在地へ遷座しました。また、羽柴秀吉の鳥取攻めの際に焼失し、江戸時代の貞享2年と元禄16年に建て替えられたと記録されています。大山祇命と啼澤女命が祀られ、大山祇命は、いざなみがかぐつち(火の神)を産んだ時にやけどで亡くなったことに怒って切った時に生まれました。大山祇命は山の神ですが、別名の和多志大神の「わた」は海の古語で、海の神を表しますので山と海の神様のようです。(陸上の立地を見てなるほど!っと思える祭神ですね)啼澤女命はいざなきがいざなみの死を悲しんで流した涙から生まれた泉の湧き水の精霊神とされています。平成20年7月29日に社叢が町の天然記念物に指定されました。例祭日: 秋例大祭は10月10日ですが10月第二日曜に獅子舞が陸上地区の一軒一軒を1日かけてまわり、玄関先で舞い、本舞は神社、海、公民館等で舞います祭神:大山祇命(おおやまつみのかみ)伊弉諾(いざなぎ)尊・伊弉冉(いざなみ)尊の子/山岳丘陵の守護神・水源水利・商売繁盛・家内安全・長寿・良縁・安産啼澤女命(なきさわめのみこと)伊奘諾尊(いざなぎのみこと)の涙から生まれたとされる神/井戸神として信仰・生命長久、新生児の守護、 死者の復活を願う人々の祈りに応える所在地:鳥取県岩美郡岩美町陸上 57甘露神社の参道から境内まで甘露神社には平安時代の天皇が体調を崩した時に、因幡国はじめ九ヶ国に甘露が降るとお告げを受けたそうで、勅使(天皇の意思を直接伝える使者)が調べると、山麓の大岩にある笹に甘露がたまっているのを発見し、勅使がこれを持ち帰って天皇に献上したところ病気が治癒し、社号を甘露神社と改称したという伝説があります。また『鳥取藩主の池田公から甘露神社に頂いたものを海賊に盗まれないように田河内神社に隠したもの』とされる謎の神輿伝説もあります。写真は田河内神社のページに掲載しました。甘露神社は権現造りで、本殿前に不思議な霊獣があり、何とも言えないかわいらしさが個人的に好きです。補足ですが、権現造り(ごんげんづくり)とは、神社の本殿と拝殿を「石の間」や「相の間」と呼ばれる幣殿でつなぐ建築様式です。岩美町陸上の甘露神社を訪ねて…伝説と出雲型の阿吽の狛犬
-
院内の熊野神社におまいりに行こう!鳥取県岩美郡岩美町院内176に位置している熊野神社は、伊邪那岐尊(いざなぎのみこと)と伊邪那美尊(いざなみのみこと)を祭神としており、荒金川の南側の山すそに位置し、柵を避けて石の鳥居をくぐって石段を登ってお参りします。熊野神社の歴史は古く、白雉3年(653年)に社殿が建立されたとされています。もともとは院内・荒金・黒谷を新宮保と呼び、荒金に国の峯行者堂を設けた際に、この地に熊野権現を勧請したと伝えられています。その後、寛延元年(1748年)に熊野権現一宇が成就しました。明治元年には「熊野社」と改称され、後に「熊野神社」となりました。現在も地元の人々に親しまれており、例祭は毎年3月19日に行われ獅子舞があります。自然に近い場所ですので獣に遭遇しないよう注意をしておくことを推奨します。例祭日:3月19日祭神:伊弉諾尊伊邪那岐命(いざなぎのみこと:伊邪那美命とともに国生みをした男神)/夫婦円満、縁結び、殖産振興、 厄除け伊弉冉尊伊邪那美命(いざなみのみこと:伊邪那岐命とともに国生みをした女神)/子宝や安産祈願、縁結びの神境外には稲荷大明神(宇可之御魂神うかのみたまのかみ)/五穀豊穣の神荒金山神(素戔嗚命すさのおのみこと)/暴風雨や厄除けの神八幡宮(誉田別命ほむたわけのみこと)応神天皇の生前の名・母は神功皇后/武勇と学問の神が祀られていた記録があります。所在地:鳥取県岩美郡岩美町院内176院内付近には荒金鉱山や荒金行者山、移住者が経営するカフェ、天地有氣がありますので併せてご案内します。
-
浦富の熊野神社を知っておまいりに行こう!鳥取県岩美町には熊野神社が2社ありますが、ここでは浦富に鎮座する熊野神社について記載します。祭神は若一王子「若宮」と称し、天照大神、伊弉諾尊いざなぎ、伊弉冉尊いざなみ 速玉男命 泉事詳男命(泉津事解之男。) 武甕槌命を祀っています。古事記でいうはじまりの皆さまですね!住宅街ですが、一歩はいると静かな杜という感じで心が落ち着く参道で拝殿には鳥取藩主の家老であった鵜殿家の家紋があります。平成20年7月29日に社叢が町の天然記念物に指定されました。例祭日:7月21日. 秋祭11月3日祭神:天照大神(あまてらすおおみかみ)/太陽神、天皇家の祖先神國常立命(くにのとこたちのみこと)/神世七代の初代神・国土の守護神伊弉諾尊伊邪那岐命(いざなぎのみこと:伊邪那美命とともに国生みをした男神)/夫婦円満、縁結び、殖産振興、 厄除け伊弉冉尊伊邪那美命(いざなみのみこと:伊邪那岐命とともに国生みをした女神)/子宝や安産祈願、縁結びの神速玉男命(はやたまのおのみこと)伊邪那岐命の吐いた唾から生まれた子/悪縁を絶ち、けがれを祓い、良い縁を整える神泉事解男命(ことさかのおのみこと)伊邪那岐命の吐いた唾から生まれた神が速玉男命で、次に掃きはらって生まれた神が事解男命/決断と再出発、悪縁消除を象徴する神武甕槌命(たけみかづちのみこと)雷神/日本建国、勝利、武道の神・肉体的、精神的な強靭さ・旅の安全祈願所在地:岩美町大字浦富529 熊野神社歴史について個人的に岩美町誌などで調べた情報と地元の方に伝え聞いたことですが、熊野神社は大字浦富字照山529鎮座し創立は承和年間834年から前国常立命一神を御祭りし、社号を天照大神が【若一王子】と称して祀られ、のちに南紀熊野宮から伊弉諾尊いざなぎ、伊弉冉尊いざなみ 速玉男命はやたまのをのみこと 泉事詳男命(泉津事解之男。ミヅコトワケオノミコト) の四神を勧請して合祀しました。勧請:他の土地に分霊として神を迎えて祀ること 合祀:複数の神仏を一つの神社や寺院で共に祀ること例点別々の神社で祀られていた神々を一つの神社に合祀することで、神々の力を共有し、地域の人々に幅広いご利益をもたらすことがあります。板谷播磨守が本町桐山城に居城してから 同隠岐守嫡子播磨守光成など代々熊野神社を崇信し、熊野神社に剣刀を奉納、寛永以降(1632)池田光仲が藩主のときに因伯国家老鵜殿氏が鵜殿大隅陣屋を築いたころから代々崇敬があつく、社殿の造営や武器、宝物などを奉納して享保年間から(1716~)神幸祭礼を行い始め、祭祀料として田地七反歩を寄進し社領六石をつけました。※文化十年(1813)5月に火事が起こり記録が消失文久3年(1863)9月に鵜殿大隅の発意により 鳥取藩主池田慶徳氏が藩の学館に奉祀している武甕槌命を合祀明治4年(1871)熊野宮と改称し、その後さらに熊野神社と改称次いで村社へ。明治40年(1871)4/27に神饌幣帛料供進神社(しんせんへいはくりょうきょうしんじんじゃ)として指定む、難しい文面。。神社系の解説って難しいです。ガイドではわかりやすく伝えたいのでもっと噛み砕いた言い方を試行錯誤しないと!さて、ここからは境内についてです。熊野神社の拝殿右側の目立たないところに、傘と火袋部分が壊れてしまった石灯籠があり、その灯籠の竿部分には【竹・笹の葉】が彫刻された珍しく、そして縁起の良いデザインになっています。竹は真っ直ぐに育ち、折れない強さから、迷いなく一直線に進む心の強さを意味しますので、そういった意味を含んで彫られたのかなぁなんて得意の妄想をしています。また大きなウロもあったので神秘的で趣もあり好きだったのですが、台風の影響で折れてしまいましたので折れる前のウロを載せておきます。岩美町熊野神社の歴史と縁起の良い石灯籠熊野神社は天照大神が祀られていることもあり、自然災害から護ってもらうよう頻繁におまいりしていました。夏場は涼しいのですが蚊がすごく多いため手を合わせている数秒でも蚊の歓迎を受けますので虫よけスプレーやハッカオイル塗布などお勧めします。
-
許野乃兵主神社を知っておまいりにいこう!許野乃兵主神社は岩美中学校・岩美高等学校の裏山、鳥取県岩美郡岩美町浦富686に鎮座し、祭神は大国主神 素盞嗚尊で例祭日は4月は8-9日です。急こう配の石階段を上がると春は桜の花が咲いていて綺麗です。コノノヒョウスノジンジャと呼びますが以前はコノノヒヤウズジンジャと呼ばれていました。許野ノ兵主神社の写真手水舎は湧き水です!石段を登り切って振り返ると狛犬とともに校庭が望めます。岩美町太田・本庄地区の神社などを歩き、地形の変化や歴史、植物や暮らしを知る旅でガイドブックなどには載っていない、地元の方やコアな歴史好きの方に向けたコースのまち歩き記事を併せてご覧ください許野ノ兵主神社〜美取神社〜道しるべの石碑〜太田薬師堂〜本庄観音堂
-
護邑神社にお参りに行こう鳥取県岩美町洗井地区にある護邑神社(ごゆうじんじゃ)は洗井集落の山腹の石の鳥居をくぐり、、石の階段を登った先に鎮座しています。歴史としては1335年(建武2年)2月に高草郡(たかくさぐん)の松上大明神を勧請して建立したとされ、また、天正時代に戦争による火災で社殿が焼失し1643年(元禄6年)と1821年(文政4年)に再建されたと伝えられ、明治7年には松上大明神から洗井神社と改称され、のちに鳥越神社、銀山神社、蕪島神社、横尾神社を合祀し、大正2年に護邑神社(ごゆうじんじゃ)と改称しました。例祭日は10月9日、春祭は4月9日祭神は稲倉魂命(うかのみたまのみこと:五穀や食物をつかさどる穀物の神・農耕の神、商工業の神、商売繁盛の神として信仰)大山津見命(おおやまつみのかみ:伊邪那岐命と伊邪那美命の子:山岳丘陵の守護神、水源・水利の神)須佐之男命 (すさのおのみこと:伊邪那岐命の子で天照大神の弟:災害や疫病の厄除け、縁結び、安産・子育て、心身の成長や成熟、心身健全、技芸上達、 夫婦円満)伊邪那岐命(いざなぎのみこと:伊邪那美命とともに国生みをした男神:夫婦円満、縁結び、殖産振興、 厄除け)伊邪那美命(いざなみのみこと:伊邪那岐命とともに国生みをした女神:子宝や安産祈願、縁結びの神)所在地:鳥取県岩美町大字洗井1709-1
-
坂上神社の歴史を知ろう!鳥取県岩美町恩地字坂上にある坂上神社はさかげじんじゃと呼び、神産日神、天児屋根神、興登魂日神、天押雲命、天種子命を祭神としています。坂上神社の歴史については、勧請年代が不詳であるため、正確な創建年は分かりません。しかし、古くから「五所大明神」と称されていました。かつて神社の裏山に猪尾山城があり、城には坂上定六という槍の名手がいて、天正9年の羽柴秀吉の因幡攻めの時に姫路に出向いたといわれています。そのことから集落が『坂上:さかげ』と名付けられ猪尾山城内(大字恩志内坂上字五社ノ宮)に祀られていた神社が遷座されました。明治5年(1872年)に「坂上社」と改称され、同年7月に「坂上神社」という名称になりました。昭和26年(1951年)に現在地に移転し、幣拝殿が建立されました。境内までの参道は標高自体は高くありませんが石段含めて険しい箇所がありますので本格的な登山同様の靴でいかれることを推奨します。また、雑木林の山道ですので獣にもご注意ください。例祭日:4月1日祭神:神産日神(かみむすびのかみ)/良縁祈願・万物生成の働きを担う神天児屋根神(あめのこやねのかみ)中臣氏の祖神/国家安泰、学業成就、出世開運、家内安全、智恵、神事、文学、言葉、防衛、 歌曲、芸能興登魂日神(こごとむすびのかみ)天児屋命(あめのこやねのみこと)とも呼ばれ中臣氏と藤原氏の祖神/国家安泰、学業成就、出世開運天押雲命(あめのおしくもねのみこと)天児屋命の子/飲料水に関する御利益、 浄めに関する御利益天種子命(あめのたねこのみこと)天押雲命の子、中臣氏の祖神。 天児屋命の孫/所在地:鳥取県岩美郡岩美町恩志636
-
佐彌乃兵主神社の歴史を知ろう!鳥取県岩美町の河崎にある佐彌乃兵主神社(さみのひょうずじんじゃ)は蒲生川と国道9号線の間にあり、佐彌(さみ)は佐美(佐弥)とも書かれ、人の姓(佐美朝臣/崇神天皇の子)であり古代の地名でもあり(小字名は「佐彌屋敷」)、天照大神を祭神としています。神社の由緒によると、創立年代は不詳ですが、延喜式神名帳(927年)に記載されている神社で、平安時代から社名が一貫しているとされています。また、天仁2年(1109年)には、鳥羽新帝が神霊を貢ぐことを望んだという記録があります。現存最古の棟札は享保11年(1727年)のもので、大正14年に本殿や諸社殿が建立されました。現在も地元の氏神として親しまれており、例祭は毎年4月13日に行われています例祭日:例祭4月13日・秋祭10月13日祭神:天照大神(あまてらすおおみかみ)/太陽神、天皇家の祖先神境内 恵比寿社・事代主命(ことしろぬしのみこと)大国主命の子/天皇を守護する託宣の神・七福神のえびす様と同一視され代表的なご利益は「豊漁祈願」所在地:鳥取県岩美郡岩美町河崎211兵主神は、もともと中国大陸から渡って来た武をつかさどる神です近隣にはきなんせ岩美・喫茶めだかの学校・新井・許野乃兵主神社・美取神社などがあります。
-
白地神社におまいりに行こう!鳥取県岩美町白地地区にある白地神社は白地集落の山裾にある鳥居をくぐり、急こう配の石段を上るとまっすぐそびえたつ木立の中にあります。創建年は不詳ですが、『因幡誌』(1795年)には「氏神 童動大明神」と記されていて明治初年に白地神社と改称されました。小山神社(大帯姫命)と童動神社(素盞嗚命)を合祀したもので大正6年に一度御湯神社に合併されましたが、昭和24年12月に分離され、社殿を再建して遷座しました例祭日:12月1日祭神:素盞嗚命 (すさのおのみこと:伊邪那岐命の子で天照大神の弟)/災害や疫病の厄除け、縁結び、安産・子育て、心身の成長や成熟、心身健全、技芸上達、 夫婦円満大帯姫命おおたらしひめのみこと:神功皇后の別名)/子育大願や安産祈願所在地:鳥取県岩美町大字白地613白地神社付近には、白地で育った野菜や小麦を使用したおいしい手作りケーキのカフェ、A lot・白地さんがあり、田園風景を望みながらゆったりした時間が過ごせます。
-
諏訪神社の歴史を知ろう!諏訪神社は鳥取県岩美町にある諏訪神社は、まっすぐ高く伸びる杉林が厳かな雰囲気を醸し出しています。建御名方命、菅原道眞、玉垂命を祭神としています。この神社は正徳3年(1713年)に創立されたとされています。諏訪神社はもともと「諏訪大明神」と呼ばれていましたが、明治元年に笹下の高良大明神(玉垂命)と天神山の天満宮(菅原道真)を合祀し、諏訪神社と改称されました。昔から軍神や開拓の神として崇敬されており、後醍醐天皇が1333年に名和長年(なわながとし)の助けを得て、隠岐より脱出して還幸の際には勅使が派遣され祈願が行われたと伝えられています。また江戸時代に天然痘が流行した際に、疱瘡の神である建御名方命に治癒祈願にたくさんの方がお参りされたそうです。例祭日:3月29日祭神:建御名方命(たけみなかたのみこと)大国主神(おおくにぬしのかみ)と高津姫神(たかつひめのかみ)の子/水神、風神、狩猟神、農耕神、軍神、開拓の神、疱瘡の神菅原道真/学業成就、厄除け、冤罪を晴らす、正直・至誠、農耕、 芸能の神玉垂命(たまたれのみこと)/縁結び、夫婦和合の神・合格祈願や、商売繁昌等の勝運祈願所在地: 鳥取県岩美郡岩美町池谷490ちなみに岩井温泉を開湯し、湯治した藤原冬久の皮膚病も天然痘だったのではないかともいわれているようです。
-
高住神社の歴史を知ろう!鳥取県岩美町高住集落の山裾にある高住神社はいわみ八宝の一つである特産物、新雪梨の梨園の手前に鎮座しています。古くより姫大明神と称される高住村の氏神で現存する棟札には元和9年(1623年)に創立され、山名時氏が二上城の城主の際1712年に、高野神社の如く二上山から移されたものだとされています。また「宝暦四年(1734年)十一月奉建立姫大明神一宇成就」と記されています。明治元年に高住社と改称され、その後さらに高住神社と改称されました。この神社は、地元の氏神として信仰を集めており、特に農業の神様として崇敬されています。また、高住神社は毎年秋に行われる「高住神社秋祭り」で有名で、地元の人々にとって重要なイベントとなっています。畑の野菜の収穫、二十一世紀梨、新興梨、王秋梨、新雪梨と8月末から順番に3月まで食べれる梨の豊作祈願でもありますね。例祭日:3月29日祭神:木花開耶姫命(このはなのさくやびめのみこと)天照大神の孫の瓊瓊杵尊の妻/火難除け、安産・子授けのほか、農業、漁業、織物業、酒造業、海上安全・航海安全など素戔嗚命(すさのおのみこと)/暴風雨や厄除けの神所在地:岩美町大字高住字日野谷口205
-
高野神社の歴史を知ろう! 鳥取県岩美郡岩美町延興寺69に鎮座する高野神社の祭神は、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)、国常立尊(くにのたつのみこと)、天照大神(あまてらすおおみかみ)、誉田別命(ほんだわけのみこと)、倉稻魂命(くらいなだまのみこと)です。高野神社は『延喜式』神名帳(927年)に記載されている神社で、近世までは「鐘撞大明神」と呼ばれていました。『因幡誌』によれば、二上山の南の尾にある高野坂からこの地に移されたと記されています。また、白河天皇の承暦四年(1080年)六月の条にも「因幡国高野神」として記録されています。(高住神社も同様)貞享元年(1684年)九月に新しい社殿が建立されたことが棟札に記されています。国常立命はもともと摂社で「若一王子」と呼ばれており、承応二年(1653年)八月に建立されたことが棟札に記されていますが、明治元年に「釜戸神」と改称されました。また、末社の神明宮(天照大神)、八幡宮(誉田別命)、神位社(倉稲魂命)を合祀して「山ノ神」と称していましたが、同年8月にこれらの四柱の神々を本社に合祀し、「高野神社」と改称されました。巨木がありながらも開かれた明るい境内には奉納された手水岩があり昭和15年に『皇紀二千六百年記念の手水』と彫られています例祭日:4月9日・秋祭9月9日祭神:瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)天照大神の孫/五穀豊穣、商売繁盛、国家安寧、 殖産振興国常立尊(くにのたつのみこと)/国土の安定や子年の守り天照大神(あまてらすおおみかみ)/太陽神、天皇家の祖先神誉田別命(ほむたわけのみこと)第15代応神天皇の事・神功皇后の息子/武運長久、国家鎮護、学問成就、家運隆昌倉稻魂命(くらいなだまのみこと)伊奘諾尊と伊奘冉尊の子/五穀豊穣、商売繁盛、農林業繁栄、諸産業隆昌、 諸芸上達所在地:岩美町大字延興寺69
-
高山神社の歴史を知ろう!鳥取県岩美町の高山集落東側にある高山神社は御神木の杉や、古木の椎の木、ヒノキが残り、国道近くでも喧騒が消え、虫の音や風の音だけの静かな空間を感じることができます。高山神社の勧請年代は不詳ですが近世まで「八幡宮」または「正一位八幡宮」と称されていました。貞享5年(1688年)と天明8年(1788年)に社殿が建立された際の棟札が現存しています。明治5年2月に「高山社」と改称され、さらに明治7年に「高山神社」となりました。もともと社地は山中の大字高山字本丸屋敷にありましたが、昭和34年の伊勢湾台風により倒壊しました。その後、公民館に奉斎される時期を経て、昭和54年4月に現社地に新たな社殿を造営して奉遷されました。例祭日:4月5日祭神:誉田別命(ほむたわけのみこと)第15代応神天皇の事・神功皇后の息子/武運長久、国家鎮護、学問成就、家運隆昌所在地:岩美町大字高山790足元がコンクリートで参道にも手すりが整備されています
-
田後神社を知っておまいりに行こう!田後神社は、漁港から続く参道が港町らしく、細い集落を通り勾配のきつい階段をあがった景観のよい高台に位置します。1682年から荒砂神社の分社として建てられ、その後明治3年(1870)に田後村となったことから、神社も浦富から独立し、荒砂神社から漁業本来の神様である恵比寿様のみを氏神として持ち出してお祀りしており、田後の祭は「喧嘩祭り」と言われ漁協前の広場で田後の10地区の氏子衆が、神輿と御船に分かれて激しくぶつけ合い一年の安全・平穏、豊漁を祈願します。アニメfree‼の聖地巡礼としても非常に人気の高いスポットでストーリーと答え合わせ・比較をしながら風景に感動されています。田後神社の風景
-
田河内神社を知っておまいりに行こう!鳥取県岩美町田河内地区に鎮座する田河内神社は甘露神社の分霊(大山祇命)を勧請(かんじょう・他の地から分霊を移すこと)して安政2年(1855)に本殿が建立され、昭和27年に拝殿が建立されました。また神輿を格納している倉庫もあります。祭神は大山祇命(おおやまつみ)、脚摩乳命(あしなづち・古事記では足名椎命と呼ぶ大山祇神の子)です。田河内神社と甘露神社の関係田河内集落は24世帯あったそうですが2017年の時点では6世帯になっていますが、不思議なことに、24世帯同じ苗字の家が一軒もないそうです。この神社には『謎の神輿がある』とされていていわれの一つには、『鳥取藩主の池田公から甘露神社に頂いたものを海賊に盗まれないように田河内神社に隠したもの』とされているそうです。その他、昔に田河内地区が栄えていた時に直接頂いたものらしいという説や、隠したのではなく移しただけという説もあり、『謎の神輿』とされています。江戸時代の宝物がこのように残っていること自体貴重ですね。近隣情報雨乞いの神様でもある石龍(石竜)さんは陸上川に沿ってできた道路沿いにあるのですが、日照りが続いたときに、この石竜さんにお参りすると三日の間に雨が降るといわれ但馬地方の農家さんも参られたそうです。また、大水無谷林道にある、ハガキの木(タラヨウ)にも行ってきた話はこちらに掲載しています。陸上川に沿って~陸上鉄橋~石龍さん~田河内集落
-
-
八幡神社にお参りに行こう鳥取県岩美町馬場地区の八幡神社(はちまんじんじゃ)は、古くから山城国男山八幡宮(石清水八幡宮)を勧請してきた歴史があり、社の記録によると810年ごろ勧請したのちに1813年ごろに、1000年祭りが執り行われたとされています。中世から八幡宮と呼ばれており、山名家が守護国の際、安藤采女正が武具など奉納しましたが現在保存されていません。明治初年には蒲生神社と称していましたが、大正2年に、相山の相山神社(須佐之男命)、蒲生の八樂神社(須佐之男命)、塩谷神社(住み吉明神・武甕槌命)を合祀し、現在の八幡神社と改称されました。境内にはスギやムクノキ、タブノキ、ケヤキなどの大木があり、美しい環境に囲まれています。また、昔は流鏑馬(やぶさめ)などの興行も行われていたとされています例祭日:10月15日、春祭は4月5日祭神:誉田別命(ほむたわけのみこと)/応神天皇(仲哀天皇と神功皇后の子)/守護(国家鎮護)神、武運長久、学問成就、豊穣祈願、 病気平癒須佐之男命(すさのおのみこと)/伊邪那岐命の子で天照大神の弟/厄除け、縁結び、安産・子育て、心身の成長や成熟、心身健全、技芸上達、 夫婦円満気長足姫命(おきながたらしひめ)/神功皇后(応神天皇の母)/子育大願、 安産祈願武甕槌命(たけみかづちのみこと)/伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の子・雷神/勝利祈願や武運長久、必勝祈願、武道成就所在地:鳥取県岩美町大字馬場105神社付近には蒲生峠、田村虎蔵(生誕の地)、、馬場の間歩があります。
-
日野神社におまいりに行こう!鳥取県岩美郡岩美町大谷に位置する日野神社は『延喜式』神名帳(927年)に記載されており、古くから地域の信仰の中心地として存在しています。また、広い参道には氏子から奉納された90基ほどの石燈籠が並んでいます。集落内にあり、他の神社と比べて平面なので参拝しやすいです。鳥取県岩美郡岩美町大谷に位置する大谷神社は『延喜式』神名帳(927年)に記載されており、古くから地域の信仰の中心地として存在しています。1573年からの天正年中、山中幸盛の第二次尼子再興運動により社殿・民家・記録が焼失しました歴史の概要創建年代: 創建年は詳しくは分かりませんが、900年頃と推定されています。中世: 中古に洪水により神社が流され、大谷の浜に遷座されました。貞享元年(1684年): 新しい社殿が建立されました。明治初年: 村社に列格され、日野八幡宮から日野神社に改称、神饌幣帛料供進社に指定されました。大正3年(1914年): 暴風のため社殿が倒壊し、大正5年に平野神社(経津主神)を合祀し再建されました。再興のために奥田亀造(岩美町名誉町民)さんが多額の献金を行ったとして日野神社再建の記念碑にも刻まれています。昭和4年(1929年): 神饌幣帛料供進神社に指定されました。※平野神社は昭和23年に分離例祭日:4月15日・秋祭9月15日・お祷祭1月12日祭神:誉田別命(ほむたわけのみこと)第15代応神天皇の事・神功皇后の息子/武運長久、国家鎮護、学問成就、家運隆昌所在地:鳥取県岩美郡岩美町大谷483日野神社付近には、大谷海岸、民宿ニュー大谷・大谷、浦富海岸島めぐり遊覧船、駟馳山(石畳道:県史跡)などがあります。
-
平野神社の歴史を知ろう!鳥取県岩美町大谷(国道9号線の南)にある平野神社は岩美町では数少ない経津主神が祭神です。近くにある日野神社同様、1573年からの天正年中、山中幸盛の第二次尼子再興運動により社殿・民家・記録が焼失しました。棟札によると1681年に本殿が再建され、武王大明神と称されていて大正3年(1914年)大谷鎮座の日野神社に合祀されましたが、昭和23年(1948年)日野神社より分離して平野神社を創立しました。例祭日:4月11日祭神:経津主神(ふつぬしのかみ)/武術の神様、勝運や交通、災難除け所在地:鳥取県岩美郡岩美町大谷1870※経津主神(ふつぬしのかみ)の別称が香取神、香取大神、香取大明神、香取さまといって香取神宮を総本社とする日本各地の香取神社で祀られているらしく、なぜ、岩美の大谷に祀られているのか…深堀してみる必要があるか、全く無関係かもしれません。
-
二上神社の歴史を知ろう!鳥取県岩美町岩常に位置する式内社で、古くは「皷大明神」と呼ばれていた岩常村の氏神です。『因幡志』によれば、現代語でわかりやすく咀嚼すると、昔、二上山には複数の神社がありました。山の頂上には鼓の神、東には天神社、南には鐘撞明神、北には八幡宮が鎮座していました。これらの神々は古くからこの地に祀られてきました。しかし、中世に山名時氏が二上城を築く際、これらの神社はすべて鼓山に移されました。そのため、この地は「鼓の宮」として拝され、「二上神社」という名前が残っています。この山は「鼓山」と呼ばれ、社前の道は「鼓縄手」と呼ばれています。これらの名前は、神々がこの地に移されたことに由来しています。との記載がありそのため、現在の場所岩常はもともとの場所ではないものの、明治初年に二上神社と改称し二上神社という名前が残っています。神社の鳥居は石造りで、狛犬も見ごたえがあり、珍しく参道から直角に拝殿と御本殿の正面があり、御本殿は権現造で、朱に塗られ彫刻と共に目を引きます。例祭日:4月3日祭神:素戔嗚命(すさのおのみこと)/暴風雨や厄除けの神所在地:鳥取県岩美郡岩美町岩常213
-
前田神社の歴史を知ろう!鳥取県岩美郡岩美町 大字長郷にある前田神社は小田川の西、集落の南側にに位置しています。この神社は元和9年(1623年)に創立されたと伝わり、古くは「三宝荒神」と称されていました。明治元年に境外末社の牛頭天王社(素盞嗚命)を合祀し、前田社と改称され、後に前田神社となりました。現存する棟札には「三宝荒神建立奉修延宝八年(1680年)三月」や「牛頭天王社内安全寛保二年(1742年)十月」と記されています。社殿には彫刻が施してあり、小さな社でも見ごたえがあります。例祭日:3月28日祭神:軻遇突智命(かぐつちのみこと)伊奘諾尊(いざなぎのみこと)と伊奘冉尊(いざなみのみこと)の子/火難除、商売繁盛、開運厄除、家内安全、 産業発展素盞嗚命(すさのおのみこと)/暴風雨や厄除けの神所在地:鳥取県岩美郡岩美町 大字長郷143番地
-
向島恵比寿神社をしって見に行こう!鳥取県岩美町浦富海岸の宮島に鎮座する向島恵比寿神社は花崗岩に朱色の鳥居が目を引く景勝地であり、うみねこが集う島でもあります。事代主神・豊玉姫命等が祀られ特に両氏の人々の崇敬者が多く、灘祭では豊漁を祈願します。向島へは潮の水位により海底に足が届いて歩いて渡れることもありますが潮の流れが複雑な場所でもあり、注意が必要です。荒砂神社の鎮座する宮島展望台から望む風景も絶景です。向島恵比寿神社の写真春夏秋冬で違う色、違う風景、違う匂いを感じることができます。仕事の息抜きにさっと数秒眺めるだけでもリフレッシュできる癒しスポットでもあります。
-
湊神社の歴史を知ろう!鳥取県岩美町岩本に位置する湊神社は創立年代は不詳ですが、口碑によれば天平年中(729年~)に創立されたと伝わります。当村は重要な港であり、毎年御手船入港の際には藩主から献幣が行われていたとされています。蒲生川の北岸にある境内までの石階段の参道を登ると大谷や岩本の集落が望め、『地域を護っている』ことが想像できてとてもいい景色です。歴史の概要創立年代: 天平年中(729年~)と伝わる。中世: 羽柴秀吉の兵火や明治元年の大火により古記録が焼失。近世: 湊大明神と称され、尼子晴久や吉川元春から篤い崇敬を受けた。明治初年: 湊神社と改称され、郷内総氏神と定められた。昭和3年: 境内を整備し、本殿など諸殿が建立された。祭神は港町らしく、彦火火出見命と豊玉姫命で、例祭は10月9日に行われます。例祭日:10月9日・春祭(お祷祭)1月13日祭神:彦火火出見命(ひこほほでみのみこと)浦富太郎のモデルになった神様・瓊瓊杵尊と木花開耶姫の子・初代天皇・神武天皇の祖父/商売繁盛や航海安全、縁結び豊玉姫命(とよたまひめのみこと)海神(わたつみのかみ)の娘・神武天皇(初代天皇)の祖母/海の神様所在地:鳥取県岩美郡岩美町岩本354
-
御湯神社を知っておまいりに行こう!鳥取県岩美郡岩美町岩井141に鎮座する御湯神社は若いときに皮膚病にかかった藤原冬久(左大臣藤原冬嗣の後裔)が、人目を避けるように山陰へたどり着き、薬師如来にも似た巫女の不思議な導きによりお湯をかぶったところ、長年の皮膚病が綺麗に治り、この岩井温泉を発見したことから、温泉の守護神として勧請したのが始まりと伝えられています。創建は弘仁2年(811)(由来は下記に追記↓)で現在の社殿は昭和4年の建立、例祭日は4月25日と秋祭りが10月13日、また3月の春祭り初午には麒麟獅子舞が奉納されます。御祭神御井神(みいのかみ、大国主命と八上比売の子ども・木俣神)/井泉の神、安産子宝、病気平癒大己貴命(おおむなちのみこと、大国主命・だいこく様)/商売繁盛、縁結び、幽世(かくりよ)を守護する神八上姫命(やがみひめにみこと、大国主命(おおくにぬしのかみ)の最初の妻)/安産や子宝、縁結び猿田彦命(さるたひこのみこと)/交通安全、教育の神が江戸時代に合祀御湯神社と岩井温泉について岩井廃寺塔跡・旧岩井小学校グランドの正面から百数十段の石段を登ると御湯神社の拝殿に着きました。拝殿本殿ともに、町内では一番大きなお宮ではないかと思われます。創建に関して諸説ありますが、棟札から1200年前の弘仁2年とされ、これをもって岩井温泉は開湯1200年としています。また、境内社の藤ヶ森神社は、御湯神社の奉遷(神体などを他の場所に移す)前からこの地に奉斎(神仏などを慎んでまつること、身を清めてまつること)されていたものと考えられています御湯神社の境内には平家の落人伝説の一つである平教経が矢を研いだ言われる「矢研石」があり岩井の奥、相山という集落には教経の墓が伝わっています。また岩井温泉ゆかむり温泉の駐車場には御湯神社の御分霊社が祀られています岩井温泉周囲のまち歩き記事も併せてご覧ください。岩井温泉のゆかむり温泉共同浴場は地元の方の毎日のお風呂としても利用され憩いの場所になっています。個人的に高温なところが魅力です。(お子様には熱めですので入る前に保護者の方が掛け湯で確認してください)日本遺産である麒麟獅子、御湯神社の舞もあります。とっとり日本遺産フォーラム麒麟獅子フェスタ2024を観覧した際の写真ですまた岩井温泉の発展に寄与した木島よしさんのお話もお読みください岩井温泉集落〜旧岩井小学校〜愛宕山頂上〜ゆかむりの塔〜愛宕山神社地元のガイドに学ぶ岩井まち歩き〜岩井温泉街の見所と歴史岩井温泉おかみ『木島よし』初代衆議院議長『松岡駒吉』を訪ねて御湯神社にゆかりがある岩井温泉周辺情報岩井屋鳥取県岩美郡岩美町岩井5440857-72-1525明石家鳥取県岩美郡岩美町岩井5360857-72-1515ゆかむり温泉 共同浴場鳥取県岩美郡岩美町岩井5210857-73-1670花屋/はなや※現在休館中鳥取県岩美郡岩美町岩井5460857-72-1431
-
美取神社の歴史を知っておまいりにいこう!美取神社は鳥取県岩美郡岩美町太田166に鎮座し、神社の鳥居の手前右手に、珍しい赤レンガの玉垣がある建物があり、改修かなにかの工事の際に、大工さんが、親切にしてくれたお礼ということで施工してくださったという説があります。(実情は要確認です)祭神は大物主神 で、例祭日は4月9日で麒麟獅子舞が奉納されます。。大物主は稲作豊穣、疫病除け、酒造り(醸造)などの神として信仰を集め、江戸時代には緑大明神と呼ばれていました。鳥居には太神社と記載され奈良県の大神神社を祀った大田田根子の子孫が、此処に住んでこの神を祀り、大神の『神』を取り、『大神社』から太田地区の名をとって太神社となった説があるようですが、その他の諸説もあり…。大正6年12月に本庄地区の北野神社の天満宮菅原道真、八幡宮三上豊範 を合祀しました。美取神社の歴史については一般的には情報が少なく、ガイドクラブで地元の人たちから情報を聞き取りしたりしたことなどをガイド時に解説させていただいています。例祭日:4月9日祭神:大物主神(おおものぬしのかみ・大国主命と同じ)/稲作豊穣、疫病除け、酒造り(醸造)などの神、商売繁盛、開運厄除け、交通安全の神菅原道真/(すがはらみちざね)/学問の神様(学業成就)厄除け、病気平癒、良縁、冤罪を晴らす、正直・至誠、農耕、芸能三上豊範:山名氏一族の三上兵庫頭豊範は道竹城の城主所在地:岩美町大字太田166美取神社の写真本庄観音堂・太田薬師堂・嶋根の水吉田達男顕彰碑きなんせ岩美道竹城跡と三上兵庫頭の宝篋印塔
-
彌長神社を知っておまいりに行こう!鳥取県岩美町大谷に鎮座する弥長神社は、駟馳山の麓に鎮座し、かつて日野神社の摂社でした。駟馳山ではイノシシが出没することがあり、登り階段がある神社にも出没する恐れがあり鉄柵が設けられていますので閉め忘れには気を付けてください。例祭日:旧9月12日(10月12日)御祭神:足仲彦神(たらしなかつひこのみこと仲哀天皇)でご利益は出世運、仕事運、縁結びなどとされています。所在地:岩美町大字大谷911弥長神社周辺まち歩きもオススメ!弥長神社は羽柴秀吉の鳥取侵攻の際に焼失しましたが江戸時代に再建されました。境内の入り口には可愛い狛犬が並んで護っています。中島吉兵衛由武は岩井郡の大庄屋で駟馳山への松の植林や鳥取藩主の池田光仲が岩井温泉に入湯や鷹狩りの際に自宅でもてなすなど接待をしたそうだけど52歳の時に事件が起きたのじゃ…岩井郡の百姓や庄屋を代表し、年貢米を納める郷倉の米村所右衛門に年貢の取り立てが厳しすぎる!っと藩に訴えたところ、聞き入れられるどころか、徒党を組んだということで5名が処罰(死罪)され、 中島吉兵衛由武は何とさらし首に…鳥取藩の歴史上、大庄屋が処罰されるのは後にも先にもこの一件だけだそうじゃ(詳しくは看板写真参照をみてつかんさい)大谷海岸、駟馳山トレイル、中島吉兵衛由武供養塔や小畑三号墳、一号墳の穴観音などもあわせてまち歩きしてみてください弥長神社周辺スポット駟馳山トレイル大谷海岸小畑古墳公園
-
定善寺と垣屋八幡宮について鳥取県岩美町浦富に位置する定善寺は因幡観音7番札所で浄土宗のお寺です。178号線を少し東に入った門前にある垣屋八幡宮はかつての浦富桐山城主の垣屋播磨守光成(宗管)・垣屋隠岐守恒総親子を祀っています。誓正山定善寺 宗派 浄土宗鎮西派 本尊 阿弥陀如来鳥取県岩美郡岩美町浦富1507 0857-72-1354因幡桐山城主垣屋播磨守光成(宗管)は但馬の山名氏の家臣でしたが、秀吉に降伏し、以降は羽柴方として但馬・因幡国境の水軍城の桐山城に入りました。因幡山名氏・毛利氏と何度も戦い、1580年(天正8年)には桐山城を攻めてきた毛利方の総大将牛尾大蔵を撃退、その後1581年(天成9年)には秀吉の鳥取城攻撃軍に参加し、落城後に戦の功績(軍功)により巨濃郡1万石の戦国大名となりました。その後息子である恒総が文禄元年(1592)から慶長3年(1598)にかけて、行なわれた秀吉の朝鮮出兵(文禄の役)にも軍勢参加し、関ヶ原の戦いでは西軍に属して断絶(改易:身分を取り上げられる)し、高野山に逃れて自害しました。父子2代で20年間治め、桐山城主となり浦富の城下町の初期の形態は垣屋時代に形成されたと考えられています。垣屋播磨守光成(宗管)の五輪塔垣屋播磨守光成(宗管)の五輪塔は平成7年9月26日に町の史跡に指定されました。石造の五輪塔を檜皮葺の祠で覆い、平成2年には瓦葺の建物で覆って保存されています。光成のお墓は桐山城内にありましたが現在地に改葬されています。鳥取藩主となった池田光仲の一族でこの地を与えられた池田加賀守政虎が居館を作るのに光成の墓が邪魔なため、埋葬されていた遺体を含め破却させるため、奉行人が掘り返したところ、三十余年を経たのにその姿はまるで生けるがごとく存じたといわれています。(ミイラ化)また、このお墓を掘り起こした奉行人はじめ従った者は俄かにケガをしたり、即死したり病気になったり狂病を発症したことから霊魂(光成)の怨念・祟りだと人々に伝えられています。垣屋隠岐守恒総の宝篋印塔は岩美町宇治の長安寺境内にあります宝篋印塔(ほうきょういんとう)は、鎌倉時代中期以降に各地で造られた石造りの供養塔で、お寺などでよく見られます。方形の階段状の基壇、方形の塔身、笠、屋頂に相輪を載せた塔形で、塔身の四面に古くは梵字が刻まれています。