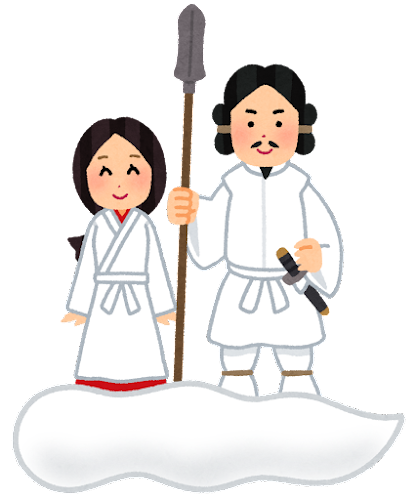因幡の菖蒲綱引きを知ろう鳥取県岩美町大羽尾で行われる伝統行事の因幡の菖蒲綱引きが昭和6年1月8日に国の重要無形民俗文化財に指定されました。保護団体名は大羽尾菖蒲綱保存会といいます。因幡の菖蒲綱引きは五月の節句に鳥取市気高町、鳥取市青谷町、鳥取市気高町宝木・水尻、岩美郡岩美町大羽尾で行われる子どもの伝統行事で地域によって内容は変わります。主に、綱に茅が多く使われていることで、その綱をもって初節の子どもの家や村中を回って歩いたり綱で地面を激しく打って回ったり、綱に災厄を負わせて海に流すことなどの特色があり、日本の綱引き行事の本質、由来を考える上で貴重な遺産であるとして国の重要無形民俗文化財に指定されました大羽尾の因幡の菖蒲綱引きの場合は祭り(旧暦の5月5日:のちに6月の第一日曜日)の前日に菖蒲、ヨモギ、茅を刈って家々の屋根の上や玄関口に置いておき、祭り当日の朝に子どもたちが大羽尾神社の境内に集めてきて綱を作り、出来た綱をもって浜に出て神社側とお寺側にわかれて綱引きを行い、そのあとにその綱で相撲を取り終わったら綱を2つに分けて神社とお寺の樹木の枝に架けます。(※平成25年から少子化により余儀なく休止しています)因幡の菖蒲綱引き:いなばのしょうぶつなひきに関する情報は文化遺産オンラインでも確認できます。牧谷のカキツバタ群落ではカキツバタの開花頃(5月上旬に)わずかではありますが自生の菖蒲の花が見受けます。
いわみのあしあと・歴史と観光と暮らしの記録
「 羽尾海岸 」の検索結果
-
-
大羽尾海岸におまいりに行こう!大羽尾神社は、鳥取県岩美町大羽尾に位置する神社でおおばにょうと呼びます。神社の起源は明確には分かっていませんが、古老の伝承によると、奥谷市郎右衛門という人物がこの地に来て、武神である武甕槌命を勧請し、一社を創設したとされています。近世には「無言大明神」または「武王大明神」と呼ばれていましたが、明治初年に「大羽尾神社」と改称されました。祭神は武甕槌命で、例祭は4月16日、灘祭は旧5月5日(現在は6月5日を過ぎた土曜日)、寅祭(秋祭)は11月の寅の日に行われています。また、重要無形文化財に指定された因幡の菖蒲綱引きもおこなわれていました。(※平成25年から少子化により余儀なく休止しています)神社は集落の中心の山腹に東北に面して鎮座しており、石段を登った先にある境内からは美しい羽尾海岸が望めます。境内には稲荷社・子持御前社・恵毘須社(港)・龍神社・金比羅社・天満宮があり、商売繁盛や大漁満足、航海安全や学業成就など、漁港で暮らす人々の心を支えています。社叢にはタブノキやヤブツバキが優先種として生育しており、参道脇には直径25センチメートルのオオバグミの老木があります。例祭日:4月16日灘祭・旧5月5日(現在は6月5日を過ぎた土曜日)寅祭(秋祭)・11月の寅の日祭神:武甕槌命(たけみかづちのみこと)雷神/勝利、縁結び、安産、国家の平和と繁栄所在地:鳥取県岩美郡岩美町大羽尾419−1大羽尾にまつわる伝承話羽尾の狸(狐)にまつわる話では大羽尾神社のお稲荷さんの話もありますのでご覧ください
-
勧学寺の歴史を知ろう鳥取県岩美町の羽尾海岸にある山陰海岸ジオパークトレイルの羽尾岬コースの入り口(昭和民宿龍神荘さん横)に位置する勧学寺は、因幡観音霊場の第九番札所として知られています。本尊は二尺五寸の十一面観音菩薩で、行基によって作られた(寄木嶋にかかりたる霊木にて刻む)と伝えられています。この観音像は、霊験あらたかで多くの信仰を集めてきました。脇士は広目天王、多聞天王です。勧学寺の歴史は古く、かつては天台宗清境寺(比叡山延暦寺)一山十二坊の一つでした。行基が開山したのち、約300年前の元禄3年、中興庵主である浄霊坊は但馬往来の通過点の細川村に浄霊橋を架け、往来の煩いを取り除きました。寛延2年(1749年)3月3日には別当龍泉院として縁起を改めて開帳、しかし、明治3年(1870年)11月に維持困難になり一時廃寺となりこの頃は大霊院末観音寺と称しました。その後、明治30年(1897年)7月、大霊院住職智光阿闍梨(仏教の位の高い僧侶や僧侶の資格を持つ者)の力により再建、現在の場所に移転されました。境内からは羽尾海岸の砂浜が一望でき、向こう岸は陸上岬と東浜海岸で海水浴シーズンには海水浴、年間通して波乗りが楽しめます。周辺には山陰海岸最大級の海食洞「龍神洞」などの自然景観もあり、この地域は、自然と歴史が融合した魅力的な場所です。〒681-0014 鳥取県岩美郡岩美町大羽尾267語句の補足「霊験あらたか」は「霊験が著しいさま」を意味する言葉で「あらたか」は「灼(あら)たか」と書きます。「灼然(しゃくぜん)」という漢字にも「神仏の利益、霊験などが著しいさま」という意味があり、「灼然」に「神仏の利益が際立っている」という意味が込められています。また霊験とは「ご利益」「利益」「利生」になります中興(ちゅうこう)は、一度衰えていたり途絶えたりしたものを復興させるという意味。別当は「別に当たる」という意味で、本来は「別に本職にあるものが他の職をも兼務する」という意味開帳とは、寺社に安置される秘仏を期間を限って公開することで、建物の維持、修復、再建費用捻出のための助成として、寺社奉行所の許可を得て行われるもの大羽尾の十一面観音菩薩と祭りについて村民の山口義則さんが観音様の功徳を世の中に広めていきたいという思いを語った記録によると、但馬の人から大羽尾には十一面観音様というあらかたなお寺様がおられるといった話が伝わっていることを知り、村民として大変うれしく思いました。戦争中には、浜辺はもとより、遠くの人々も多く参詣に来ておられ、いろいろ武運をお願いしに来られていた様子でした。昔の人の話では、漁に出て荒れてきたときなど心配な時には家族のものが船がどうなっているかを尋ねてきて『東におる船はまだ陸についていないけど安心せよ』『西に当たる船は、やがて便りがあるだろう』と導かれ大変によく当たったという事です。私たちの先祖は、本当に観音様のおかげで安心して生活をつづけてきたとおもいます。十一面観音の真言は【オンロケイジンバラ キリクソワカ】でそれぞれの梵字(サンスクリット語)の意味は唵(おん:帰命・帰依)嚕鶏(ろけい:世間)入縛羅(じばら:光明)紇哩(きり:蓮華部を象徴する種子)、娑縛訶(そわか: 成就や祈願の意)とし、直訳は「おお、世の中を照らす者よ」だそうです。つづいてただ、狸(狐)が悪事を働いて人に憑いて困らせた話を聞いています。とのこと…これは岩美の伝承話に記載します。羽尾の狸(狐)にまつわる話話を戻して大羽尾の御本尊様は、東向きに安置されています。補足:現代は御本尊の方角には、宗派や説法、慣習などによってさまざまな考え方があります。曹洞宗・臨済宗は釈迦如来を祀るため、南向きがよいとされ、浄土真宗・浄土宗・天台宗は阿弥陀如来を祀るため、東向きがよいとされ、真言宗は本山のある高野山の金剛峰寺を向けるのがよいとされ日蓮宗は特に決まった方角はないとされています。この勧学寺は天台宗であり、観音菩薩様は東か南向きに祀られるようです大羽尾の部落行事には『観音様』に関するものが多く、三夜さんの行事は1月23日、5月23日、9月23日の3回で特に5月23日の三夜さんには青年たちが観音堂に参籠し、『南無大悲観世音菩薩』と唱えて33度礼拝をし、真言【オンロケイジンバラ キリクソワカ】を唱して、心願の成就を祈り、庫裡(くり:寺院の台所や僧侶が居住する場所)で日の出まで酒宴をしてにぎやかでした。旧暦6月の17日観音祭りでは18日にかけての本尊観世音菩薩の例祭で、クジで本番・後番を定めて各々に本尊の分霊御幣を受け、僧侶は午後当番のお宅に祈念に出張します。夜は本堂尊前で護摩修行大祈祷が執行され、12時頃まで参詣者が続きます。18日は、前日に引き続き観音様の祭礼、午後5時頃より分霊の御幣を本堂に変遷する祭事があり、再度、『天下泰平・風雨順時・五穀豊穣・家内安全・心願成就』の護摩修行が執行されます御幣(ごへい)は、神道において神に捧げる幣帛(へいはく)の一種で、神様への捧げ物や神を招くための依り代として用いられます。紙または布を切り、細長い木にはさんで垂らしたもので寺や神社などで見ることができます。また7月の盆行事の最終日の17日には観音祭と称し、青年たちが主体となって33度祈念のあと、浜で盆供養の踊りをしました。33という数は、観音菩薩が衆生を救うとき33の姿に変化するという信仰に由来しています。
-
浦富海巌勝区八景詠について「浦富海巌勝区八景詠」は、鳥取県の浦富海岸を題材にした漢詩の連作で、歴史地誌学者である国府犀東(こくぶさいとう)によって詠まれました。この詩は、浦富海岸の美しい風景を称え、瀟湘八景(しょうしょうはっけい)という中国由来の風景鑑賞の方法を取り入れています。また「浦富海巌勝区八景詠」はわかりやすく『浦富八景』ともいわれています。国府犀東(こくぶさいとう)とは…石川県金沢市の左官職鹿島家に生まれ本名は種徳と言い、『犀東』は金沢西部を流れる犀川の東畔に生まれたことに由来するそうです。新聞記者を経て、官僚、天然史跡名勝記念物保存委員として浦富海岸の昭和3年に「国の名勝及び天然記念物」の指定調査に関わった漢詩人であり、歴史地誌学者です詩は序詩を含めて9つの詩で構成されており、以下の八景が詠まれています屏風岩帰帆(きはん) - 帆船が帰港する情景 陸上・東浜龍神洞晴嵐(せいらん) - 晴れた日に立ち込める霧 羽尾蔵王島夕照(せきしょう) - 夕日に照らされる風景 熊井浜/牧谷荒砂祠秋月(しゅうげつ) - 秋の月夜 浦富・荒砂神社菜種島晩鐘(ばんしょう) - 夕暮れに響く鐘の音 城原海岸睡鴨磯落雁(らくがん) - 雁が舞い降りる様子 鴨ヶ磯海岸千貫松島暮雪(ぼせつ) - 夕暮れに降る雪 網代・千貫松島虚空蔵夜雨(やう) - 夜に降る雨 網代・虚空蔵山詩に関しては鳥取県文化振興財団情報誌アルテ2008年8月の画像をご確認ください。(画像クリック↓)屏風岩 帰帆(きはん) - 帆船が帰港する情景陸上岬の部分を指し、凝灰角礫岩の断崖で六曲屏風のような景観で、海上から見上げると圧倒されます。東浜展望所から集落が遠く見える風景は、陸(集落)に近い他の浦富海岸とは違う風景です。六曲屏風(ろっきょくびょうぶ)とは、6枚の画面(扇)をつなぎ合わせた屏風龍神洞 晴嵐(せいらん) - 晴れた日に立ち込める霧凝灰角礫岩(河原火砕岩層)でできた羽尾岬の先端(羽尾鼻:正式名嶋山)にある龍神洞は二つの洞窟がありますが、中で一つにつながっています。陸から入る洞窟を裏龍神、海から入る洞窟を表龍神と読んであわせて龍神洞と呼ばれていました。最近では陸の龍神洞、海の龍神洞と呼ぶ人が多くなりました。裏龍神は崩落が多く現在はいることができませんが中に入ると円礫の浜で左側から波が打ち寄せられその先に進むと砂浜になっています。角度のある断層があり、これに沿って浸食が進んだとされています。表龍神は凝灰角礫岩に安山岩系の貫入岩があり、これが崩落して洞窟ができました。幅8m高さ10m奥行き150mさらに大岩を超えると50mあわせて200mの奥行があり、山陰海岸最大の洞窟です。龍神洞の中の様子は山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館の3D映像で観ることができます。蔵王島 夕照(せきしょう) - 夕日に照らされる風景蔵王(ぎおうじま)は熊井浜から望むことができます。荒砂祠 秋月(しゅうげつ) - 秋の月夜荒砂神社が鎮座する宮島は、現在陸続きになっていますがかつては鳥居の前にも波が来ることもありました。海に浮かぶ向島の恵比寿神社恵比寿(恵美須)神社と併せてぜひ鑑賞してください。菜種島 晩鐘(ばんしょう) - 夕暮れに響く鐘の音浦富海岸内にある城原海岸の菜種五島は、花崗岩出来た岬が長い年月をかけて浸食し、くぼみが大きくなって洞窟ができていつしか洞門になり、天井が落ちて離れ岩となって5島になり、一番大きく周囲400m高さ30mの一番大きな島を菜種島といいます。かつて菜種を積んだ船が座礁し、この島に自生したことから名づけられたという由来があります。黒松の木が茂り、ハマグルミ、トベラ、テリハノイバラのような海浜植物と共に菜の花が生育しています。睡鴨磯 落雁(すいおういそらくがん) - 雁が舞い降りる様子睡鴨磯は鴨ヶ磯といわれ、大鴨ヶ磯、椿谷、小鴨ヶ磯の3つの浜から成り立っています。鴨が磯の湾口には太郎兵衛島はじめ小さな島も沢山あり、外海に多少の波があっても湾内は静かです。太郎兵衛島のことを国府犀東は【伯良島はくろうじま】と名付けました淡紅色の石英砂(1.5mm)の浜で日によっては砂鉄が打ち上げられていることもあります。この奥にはさらに一段高い砂浜があり、その浜を離水浜といい、ずっと古い時代にできた浜で砂が黄色く風化しています。奥の崖も離水浜が形成されたときの古い海食崖です。湾の東側に小規模な波食棚があり、縦横に割れ目、節理が走っています。また西側にはノッチ(波食窪)が見られ、海底には岩の割れ目やくぼみに小石が入り、それが波によってコロコロ動いて岩を削り、だんだんと大きな穴になったポットホールも見られます。また、椿谷には柱状節理も見られます。千貫松島 暮雪(ぼせつ) - 夕暮れに降る雪網代地区の千貫松島は観光スポットしても非常に人気が高く、山陰海岸ジオパークトレイルのコースにもあり、また浦富海岸島めぐり遊覧船から間近に鑑賞することができます。この島の名の由来は、鳥取藩主の池田氏が、あの島にある美しい松をとってきて庭に植えたものに千貫差し上げようといったことからだといわれています。いわゆる、圧倒的な高額を払ってでも欲しいと思わせる美しい松の景観だったという事でしょうね。江戸時代の「千貫」の価値を令和の貨幣価値に換算するのは、物価や基準が異なるため一概には言えませんが、参考として以下の情報があります。1貫は銅銭1000枚に相当し、米の価格を基準にすると、1貫はおよそ12万円程度と試算されています。これを基にすると、千貫は約1億2000万円に相当する可能性があります。※ただし、これはあくまで目安であり、時代や地域、物価の変動によって異なる場合があります。虚空蔵 夜雨(やう) - 夜に降る雨虚空蔵山は山陰海岸ジオパークトレイルの網代側の入り口(浦富海岸自然探勝路)部分にあたります。かつて、虚空蔵山の頂上は網代の境内として知られ、その頂には虚空蔵菩薩が祀られていたとされています。さらに、山の北側に位置する断崖絶壁の海際には、通常目にするのが難しい大きな洞窟が存在しており、「海賊穴」と呼ばれていました。この洞窟には、但馬国(現在の兵庫県北部)の盗賊が潜んでいたと伝えられており、周辺地域に多大な被害を与えたとの言い伝えが残っています。浦富海岸島めぐり遊覧船では船長さんの音声ガイドで海賊穴なども観ることができます。これらの詩は、浦富海岸の自然美や歴史的背景を詩的に表現しており、地域の文化的価値を高めています。また、浦富海岸は「山陰の松島」とも呼ばれ、白砂青松の砂浜や奇岩、洞門、断崖絶壁などが点在する風光明媚な景勝地として知られていますので、この浦富八景をもとに浦富海岸沿岸をウォーキング、遊覧船と併せて鑑賞してください。浦富海岸島めぐり遊覧船
-
羽尾海岸・羽尾岬を知って遊びに行こう羽尾海岸は岩美町の浦富海岸海水浴場⇒牧谷海水浴場⇒熊井浜⇒の東側に位置する大羽尾、小羽尾地区に広がる入り江になった海岸で羽尾岬の麓にあたります。麓からは昭和民宿龍神荘さんのあたりから山陰海岸ジオパークトレイルのコースにもなっている羽尾岬の上まで登る入り口があり、羽尾岬の先端から絶景を鑑賞することもできます。今は崩落の為降りることができませんがかつては龍神洞の入り口まで降りることができていました。現在はアクティビティ体験に申し込んでガイド付きでカヌーやカヤックなどで龍神洞にアクセスできます。※羽尾海水浴場は国道178号線沿いの小羽尾地区にあたり、その他の場所では住民の方の生活に支障をきたすので路上駐車をしないよう気を付けてください。羽尾海岸ではサーファーさんや海水浴客でにぎわいますが、羽尾岬はトレイルウォークをされる方に人気のスポットです。アップダウンが少しきついところもあるので尾根に着いた時の左右に広がる浦富海岸は感動もひとしおです。羽尾岬は地質学的にも興味深い場所であり、漁港の奥にある円山の周囲はジオパーク学習でも専門家の解説付きで足を運ぶスポットです。海岸にはタフォニや凝灰角礫岩などがあり、知らない人は見落としがちですが、地質に興味のある人にとって砂浜のちょっとしたアクセントにもなっています。大羽尾で行われる伝統行事の因幡の菖蒲綱引きが昭和6年1月8日に国の重要無形民俗文化財に指定されました。(平成25年から少子化により余儀なく休止しています)タフォニとは?凝灰角礫岩とは?羽尾海岸付近のおススメスポット昭和民宿 龍神荘〒681-0014 鳥取県岩美郡岩美町大羽尾274−1マリンパーク羽尾 ダイビングサービス〒681-0013 鳥取県岩美郡岩美町小羽尾1610857723233
-
岩美町で毛嵐を観察しよう!鳥取県岩美町の海岸では、冬の寒い朝に「毛嵐」と呼ばれる幻想的な霧が発生することがあります。毛嵐は、海水と大気の温度差によって生じる蒸気霧の一種で、暖かい海面から蒸発した水蒸気が、冷たい空気に触れることで急速に凝結し、霧となります。特に以下の条件が揃うと発生しやすくなります。1. 冷え込んだ朝:冬季の早朝、特に放射冷却が強く働いた日には、気温が急激に低下します。2. 比較的暖かい海水:日本海の海水温は冬でも比較的高いため、冷たい空気との温度差が大きくなります。3. 風が弱い:風が強いと霧が拡散してしまうため、穏やかな気象条件のときに毛嵐が発生しやすくなります。4. 湿度が高い:空気中の水蒸気が多いと、霧が濃くなりやすくなります。岩美町の浦富海岸などでは、冬の朝にこの現象が見られることがあり、海面から立ち上る霧が幻想的な風景を作り出します。興味があれば、寒い冬の朝に訪れてみると、自然の神秘を体感できるかもしれません。お車の際は積雪や凍結による運転に気を付けて鑑賞してください。一枚目は浦富海岸(牧谷に近い方)から羽尾岬を望んだ場所二枚目は羽尾海岸の円山(別称 田城・たじょう)から見た毛嵐オマケ浦富海岸にある荒砂神社からみられる向島の雪景色です。ガトーショコラみたいですね
-
龍神荘さんに泊まりに行こう!鳥取県岩美郡岩美町大羽尾にある昭和民宿龍神荘さんは、羽尾海岸が目の前にい広がる抜群のロケーションです。また、お宿を出てすぐ、海水浴やサーフィンが楽しめるほか、山陰海岸ジオパークトレイルのコースにもなっている羽尾岬を歩くことができ、岬の尾根からは美しい浦富海岸(城原海岸)、東浜海岸を眺めることができます。ほぼ毎日、お宿の前の羽尾海岸の風景、海のコンディション、お宿や漁の状況、岩美町の移住情報や暮らしの様子をSNSで配信されていますのでチェックしてください。YouTubeチャンネルでは岩美町を大切に想うオーナーの人柄もよくわかりますので安心できます。龍神荘さんFacebook Instagram X(旧Twitter) YouTubeチャンネル〒681-0014 鳥取県岩美郡岩美町大羽尾274−1電話 & FAX: 0857-72-0286(10:00~18:00 / 原則年中無休・仕入れやガイドの時間帯あり)PR【ふるさと納税】特別宿泊割引券(25,000円分)岩美町限定 |鳥取県 岩美町 観光 宿 旅館 民宿 コテージ 宿泊 宿泊券 割引券 旅行【61001】 楽天で購入 【PR】鳥取県・岩美町浦富海岸シーカヤック・SUP・サーフィン体験等の予約一覧はこちら昭和民宿龍神荘さんについて昭和民宿龍神荘さんでは素泊まりプラン、朝食のみありプラン、里帰り気分に浸れる別館の一棟貸しプラン、オーナー自らが素潜り漁師として採ってくるサザエ、アワビ、カメノテなど旬の魚介類が堪能できるプラン、松葉カニプラン(シーズン限定)、お子様だけ素泊まりで大人のみ料理付きなど目的や予算に合わせて選べます。客室は2階で夏場は海風で心地よく、天気が良い日は朝陽が照らされる海を眺めながら一日が始まり、海水浴もすぐに楽しめます。また冬は雪景色を見ながらコタツでゆっくり過ごすことができ、ノスタルジックな気分に浸り日々の心のコリをほぐすことができます。昭和民宿龍神荘さんのホームページはこちらバスタオル・ボディソープ・シャンプー・リンスは備え付けありパジャマはご自身で持ち込み歯ブラシは100円で販売昭和民宿龍神荘さんの周辺の景観また珍しい地質、岩石を間近で見ることもできます。
-
羽尾の狸(狐)にまつわる話鳥取県岩美町大羽尾の勧学寺に少し記載したように、羽尾地区には狸(狐)の悪事による物語が村民の山口義則さんより伝承されていて、その3つの話を掲載します。山口義則さんが話されたのは平成13年(2001年)で当時86歳でした狸に憑りつかれた男今から70年くらい前(1930年頃・山口さんが16歳の頃)実際に見た話です。村に何の仕事もしていない、ただぽかんとして立っている老人がいました。少し高いところに手に水汲み用の柄杓をもって建っていましたが、私(山口さん)はその姿が大変面白いので少し離れて見ていました。道を歩いて通る人がやってくると、老人は時々手に持った柄杓を振って、ポカンポカンと頭を叩いてただ笑っているのです。この老人はかつて、漁師でした。ある日、延縄の釣り針につける餌を獲りに、いつものように長い竹筒を肩にかけて岩場に出ました。『ウド』という虫で、船虫と呼ばれています。この虫は岩場で群をなして素早く走り回り、人の気配がすると岩の割れ目に奥深く逃げ込むので、その岩の割れ目を煙でいぶして外に追い出し、その時に捕まえるのです。捕まえた船虫は背中に掛けた竹筒の中に入れて持ち帰るのですが、歩くたびに身体が動くのでその竹筒がブランブランして岩の角に当たるのです。その時のカーン、カーンという高い音が丸山(現在灯台がある円山の事だと思われます)に住む狸がとても嫌がり、何度も何度もカーンカーンと鳴らす上に時折ひどく高い音を鳴らすことにとうとう狸が腹を立てて、この漁師に憑りつきました。狸はちょっとだけからかってやろうといたずら気分で憑りついたのですが、薬が効きすぎたのか、それ以来この漁師は柄杓をもって立つようになったというのです。その異常な行動を見てこの漁師の家族が『法華経』の家の人に頼んで拝んでもらったのですが、3年程病は続き、死んでしまったそうです。大羽尾には今でも狸は沢山いますが、人を化かすことを聞かないようになりました。百六つ狸と百八つ狸村民山口義則さんのお話その2です。1と同じく70年以上前の夜中12時頃の出来事だそうです。Aさんは連れと飲んでいて途中ちょっと小便のために外に出て、戻ってきたときには狐が憑いていました。一緒に飲んでいた仲間たちが変だ変だ!と言い出し、羽尾の法華経を信仰する人に拝んでもらったところ私は小磯の上の百六つになる狸である!というので、なんでお前は人間に憑いたのか?と尋ねると住処にしている穴の口が影になる松の木を伐採されて、その為、雨が穴の中に入り込んできて冷たくて眠れない!腹が立って腹が立って仕方がない!逃げてやるから小豆飯と油揚げ3つを今夜から7日間田城の木ぐまのあるところに持ってこい!といったそうです。向こうの島(丸山)には百八つになる兄貴狸もいてこちらの百六つの狸と連絡しているのを見た人もあるという事です。信じるか信じないかは…お稲荷さんのりき村民山口義則さんのお話その3です大羽尾神社の拝殿に向かって左側にお稲荷さんが祀ってあります。このお稲荷さんは『りき(霊力)』のあるお稲荷さんで何か村に不幸なことがある時には喚いて知らせるようです。今から百年以上も前に、『田中の谷』が33軒焼けたときもお稲荷さんの狐が啼いたようです。その啼き声はまるで犬の遠吠えのように力のある声だったと伝わっています。羽尾地区は、羽尾海岸、大羽尾神社、小羽尾神社、勧学寺、昭和民宿龍神荘(浦富海岸・羽尾)、などのスポットがあります。また羽尾岬のトレイルウォークもおすすめです。